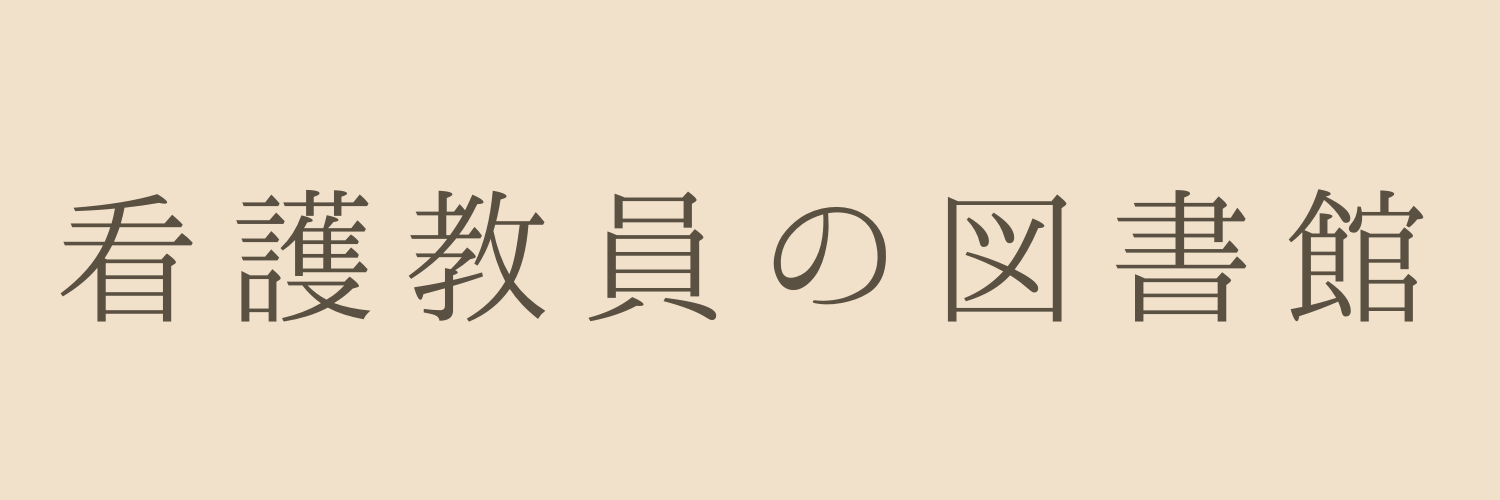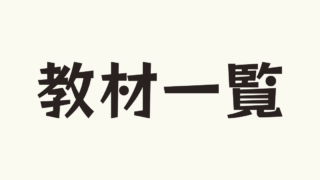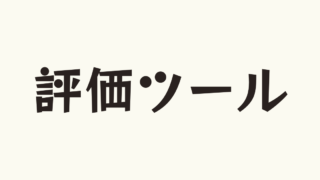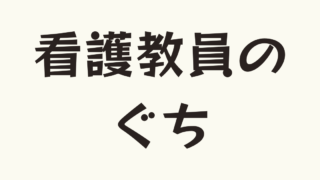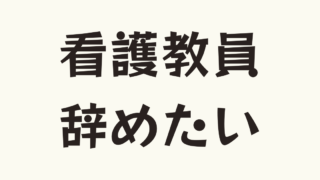看護学校教員として働く中で、こうした閉そく感を抱いていませんか?私自身も、教育現場での人間関係や業務量の多さから、何度もストレスを感じてきました。
この記事では、看護学校教員に特有の閉そく感とストレスの要因を整理し、その対処のヒントを探っていきます。
看護教員がもう限界って人は、情報収集から初めておきましょう😊💡
クリック👉看護教員がつらい・きついあなたに:おすすめ転職・求人サイト7選
1. 看護学校教員の労働環境とストレス

看護学校教員は、授業以外にも多くの業務を抱えており、評価されにくい「見えない労働」と人間関係の複雑さから、日常的に強いストレスを感じやすい職種です。
(1)評価されにくい「見えない労働」
授業以外にも多岐にわたる業務があるが、これらは時間外労働として評価されにくいことが多いです。
- 授業準備:教材作成、パワーポイント、演習シナリオ作成
- 学生対応:質問・相談・面談、実習のフォロー
- 記録業務:授業記録、会議資料、実習評価の記入
- 委員会活動:カリキュラム検討、学内委員会参加
- 学校行事:入学式・卒業式・オープンキャンパス運営
結果として、「こんなに働いているのに報われない」「教員は定時で帰れていいね」と誤解されることが、ストレスの原因になります。
(2)人間関係と前例主義が生む閉そく感
看護学校は小規模組織であるため、人間関係の硬直化や前例主義が教員のストレスを増幅させます。
意見を言いにくい雰囲気
ベテラン教員の意向が優先される
「空気を読む」文化の強さ
こうした状況は、教員の閉そく感を強め、モチベーション低下や教育の質低下につながり、ストレスを感じやすいです。さらにその緊張感が、学生への指導スタイルにも影響し、教育現場全体の閉そく感を強めることになります。
2.看護学校教員ができるストレス対処法

(1)当たり前を疑う
(2)小さな本音を伝える
(3)外部の風を取り入れる
(4)セルフケアを意識する
まとめ|看護学校教員の人間関係ストレスを言葉にする
看護学校教員は、労働環境の不透明さや人間関係の複雑さから、強いストレスを抱えやすい職種です。「もう辞めたい」と思うほど追い込まれる前に、まずはそのストレスの正体を言葉にすることが大切です。閉そく感や違和感を共有することが、教育現場を少しずつ変えるきっかけになります。
具体的には、次のような行動が有効です。
こうした小さな積み重ねが、ストレスを軽減し、教育現場の風通しを少しずつ良くしていきます。
最後に強調したいのは、あなたが抱えているストレスは決して一人だけのものではないということです。多くの看護学校教員が同じように悩み、模索しながら日々を過ごしています。一人で悩まず、ストレスをため込まないようにしましょう。
\✨まずは情報収集から✨/