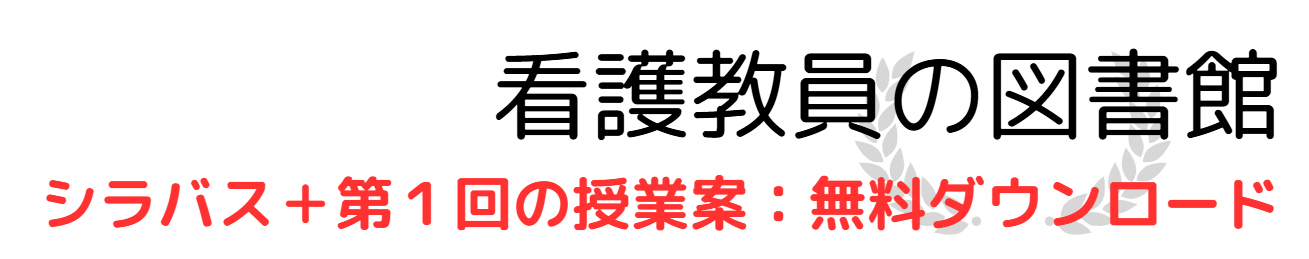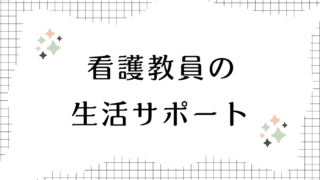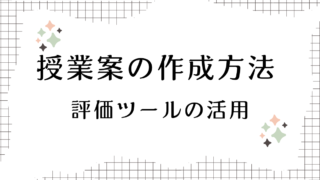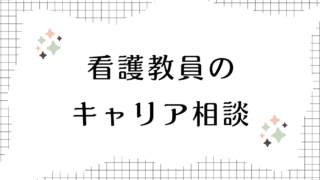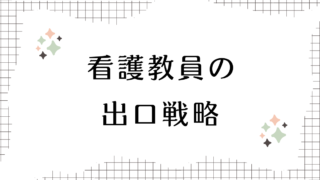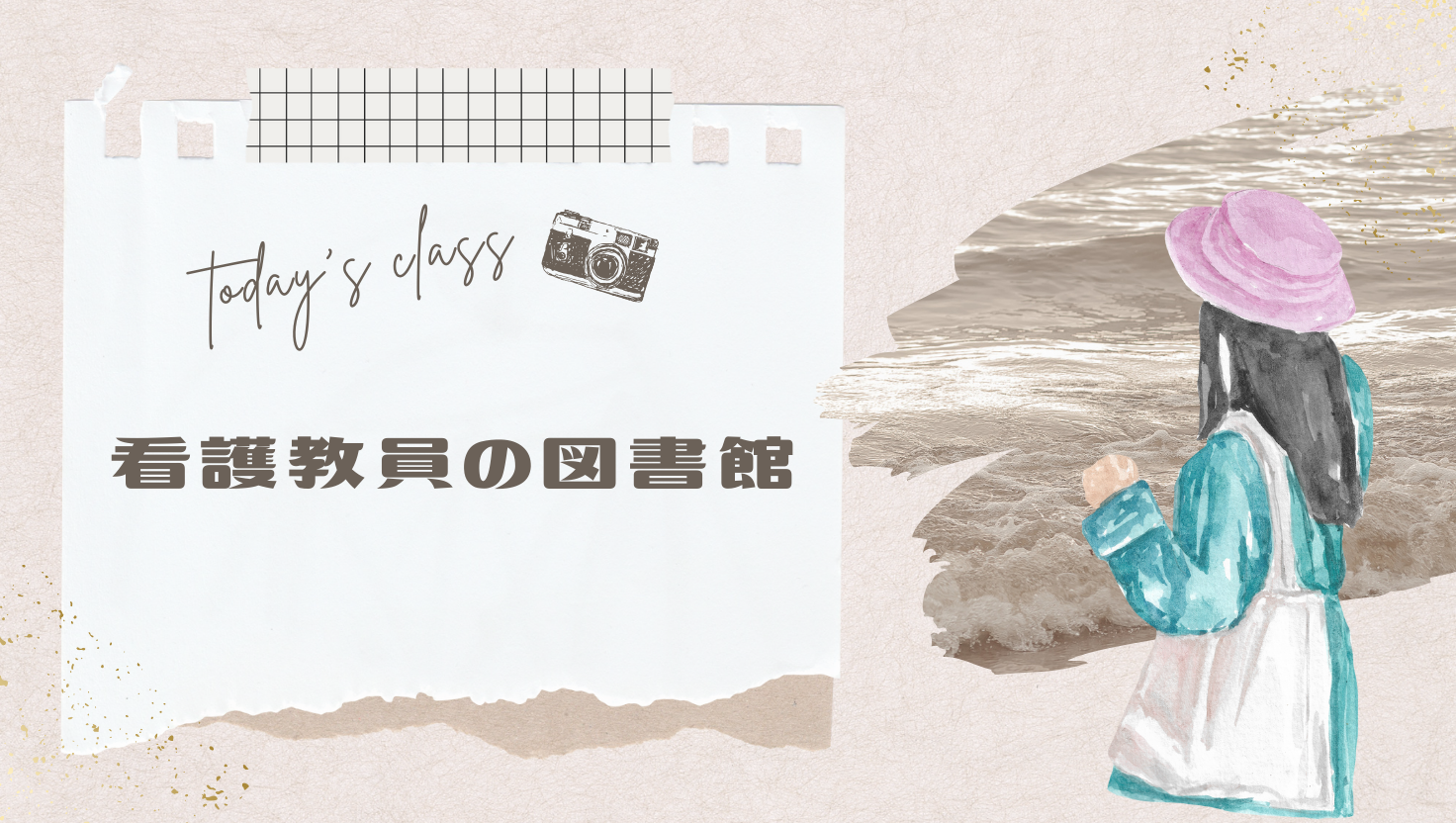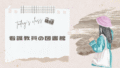実習指導において、最も気を使う場面のひとつが「病院との関係づくり」。
教員として学生の学びを支えながら、実習病院の協力を得る――まさに両者の橋渡し役です。
でも、実際は…
- 「病棟に入った瞬間から空気がピリッとしてる…」
- 「スタッフの反応が冷たくて、何を話せばいいか迷う」
- 「またこの学校か、って思われてそうで胃が痛い」
そんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか?
ここでは、実習病院と良好な関係を築くための5つのポイントと、現場で起こりがちなリアルを交えてご紹介します。
感謝と敬意を、言葉にして届ける
▷よくある現実
「学生のことで精一杯で、ついスタッフさんへの声かけが後回しに…」
そんなときもありますよね。
▷でも、実は
スタッフは「こちらが協力していることに気づいているか」をけっこう見ています。
感謝の気持ちは、口に出して初めて伝わるもの。
▷こんなひと言で変わる
- 「今日もご指導ありがとうございます」
- 「学生が○○さん(看護師)からの声かけにすごく励まされてました」
- 「忙しい中、時間をつくっていただきありがとうございます」
“よく観てくれている教員だな”という印象が、信頼のきっかけになります。
情報共有は「タイミング」と「伝え方」が命
▷現場でありがちなこと
- 実習初日、「この学生、実はちょっと心配なタイプ」と後出し情報がくる
- 教員からの説明があいまいで、病棟が困惑
▷じゃあ、どうする?
- 実習前:学生の特性(緊張しやすい、積極性が弱いなど)を簡潔に共有
- 実習中:トラブルや体調不良は“即報告”
- 実習後:学生の変化・成長をスタッフに伝えると喜ばれます
また、口頭+メールなどの書面でフォローすると、相手の安心感がぐっと高まります。
学生トラブルには「すぐ対応」が鉄則
▷リアルに起きるのはこんな場面
- 「患者さんに失礼な言動があった」と報告を受けた
- 「実習態度に問題あり」と言われたけど、学生は「そんなつもりは…」と否定
▷このとき教員に求められるのは
- とにかく“まず反応する”こと
- その場で「確認します」「対応します」と伝え、後でしっかりフォロー
「教員がちゃんと見てくれている」と病棟に感じてもらえると、関係性は大きく変わります。
実習のねらいを、現場と共有しておく
▷ありがちなすれ違い
- 「この学生、全然動けないけど大丈夫?」
- 「清拭やらせたら失敗したみたいで…」
でも、実はこの実習の目標が「看護過程の展開」や「患者理解の深まり」だったとしたら…
そこまでの技術習得を求めていない場合も多いんです。
▷だからこそ
「今回は“患者の生活背景を理解する”ことを中心に指導しています」
といった簡潔な説明があると、スタッフの受け止め方が変わります。
関係づくりは“実習中”だけじゃない
▷やっておくと信頼につながること
- 実習終了後に「学生の成長ポイント」をお礼とともに伝える
- 学年末にお礼状や訪問あいさつをする
- 病院主催の研修や委員会にもできる範囲で顔を出す
こうした普段からのつながりがあると、トラブル時にも柔軟に対応してもらいやすくなります。
まとめ:信頼される教員とは?
病院スタッフは、学生の言動と同じくらい、教員の立ち振る舞いを見ています。
- 「学生の状態をちゃんと把握しているか」
- 「問題が起きたときに責任を持って対応しているか」
- 「感謝の気持ちや目的を明確に伝えているか」
この3点を押さえておくだけでも、信頼関係は着実に築けます。
おわりに
学生の育ちを支えるために、現場とどう手を取り合うか。
教員の“立ち回り”は、まさにそのカギを握っています。
無理をせず、自分なりの言葉で、病院とのつながりを少しずつ育てていきましょう。