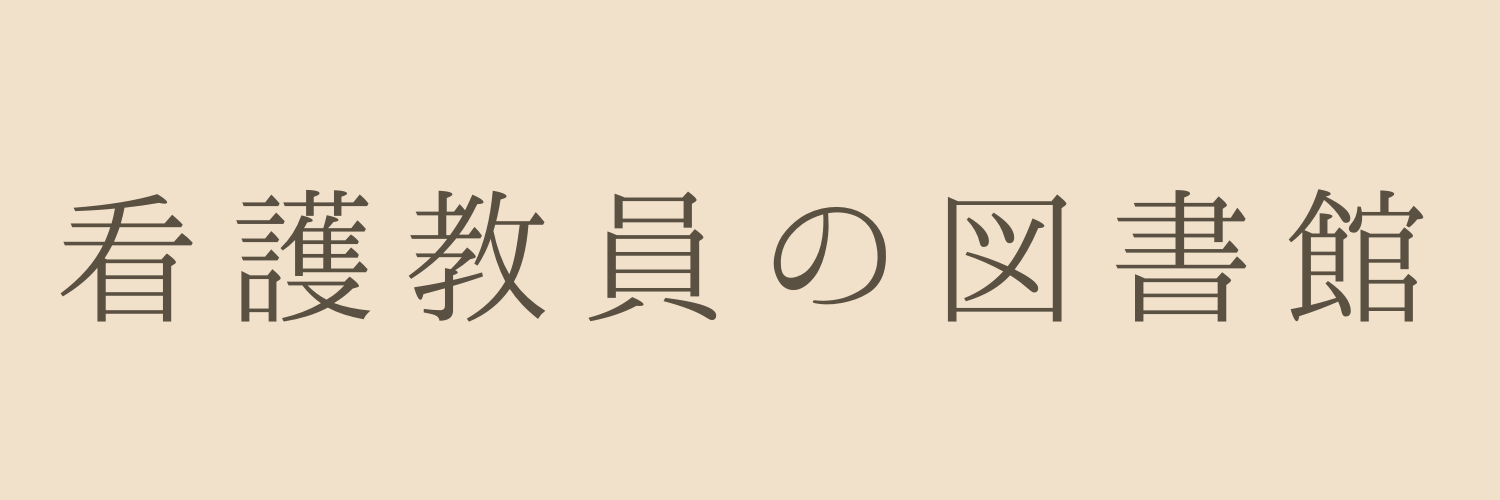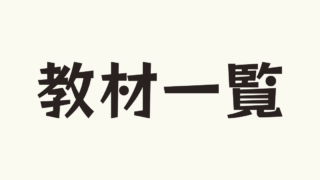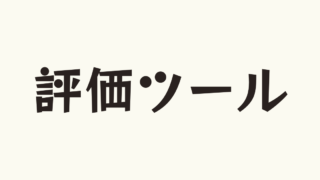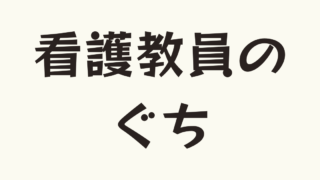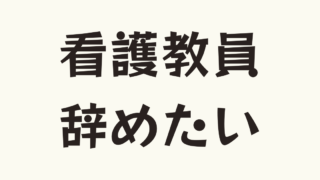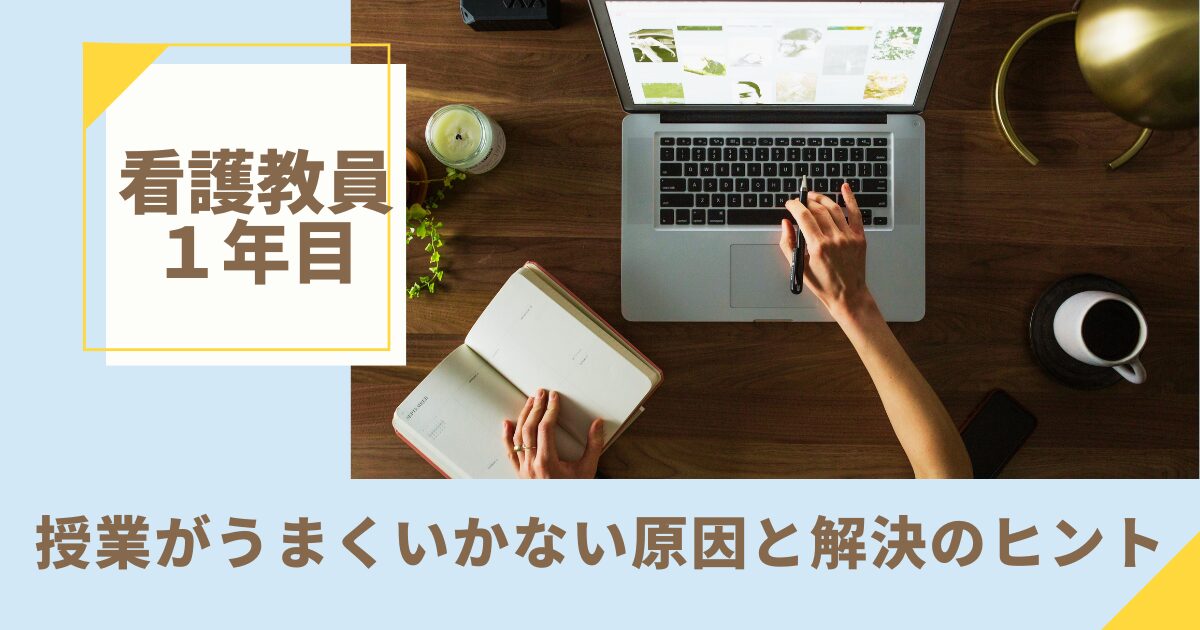看護教員1年目「授業がうまくいかない…」「学生が反応してくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
臨床経験は十分でも、教壇に立つと全く別の世界。私自身も、1年目は毎回戸惑いと不安の連続でした。
この記事では、看護教員1年目が授業でつまずく理由と、授業づくりのコツや実例を紹介します。
看護教員1年目にありがちな授業の悩み

臨床経験があっても教壇は別世界
私は臨床経験7年。新人指導や患者説明には自信がありました。しかし、教壇に立った瞬間、状況は一変しました。
教室にいるのは学生ですが、反応はゼロ。話すのは私だけ。これが、多くの看護教員1年目が直面するリアルな壁です。
授業が伝わっていないと感じる具体例
授業中の学生の様子は、次のような状態が多く見られました。
たとえば「清潔援助」の授業では…
- 私:洗髪や清拭の手順、観察ポイントを教科書通りに説明
- 学生:無言でメモも少ししか取らず、目線も合わせない
- 私:「…これって臨床でどう活かせると思う?」👉学生:沈黙
- 結果:話すのは教員だけ。学生の理解度や関心が見えず、不安が募る
この状態が続くと、「自分の授業は本当に伝わっているのか?」と毎回悩むことになります。や観察ポイントを教科書通り説明しても、学生の反応は薄く、毎回「これでいいのかな」と不安になっていました。
授業づくりで意識すべき「逆算思考」

「何を話すか」より「学生が何をできるか」を考える
授業をうまく設計するには、伝える内容中心ではなく、学生の学習ゴールから逆算することがポイントです。
良くない授業方法
良くない授業である理由
良い授業方法
この逆算思考を取り入れたことで、授業の組み立てが格段にやりやすくなり、学生の反応も見えるようになりました。
授業づくり4ステップ(清潔援助の例)

ステップ1|テーマを設定する
- テーマ:清潔援助
→ 学生が学ぶ内容の大枠を決める。授業全体の方向性を明確にする。
ステップ2|授業の目的を決める
- 目的:清潔援助の意義と、安全・安楽への配慮を理解する
→ 学生が授業を通して何を理解してほしいかを具体化する。
ステップ3|具体的な学習目標を設定する
授業後に学生ができるようになることを具体的に示す。
ステップ4|授業構成を考える(90分)
授業時間を効果的に配分し、指導方法を組み合わせる。
| 10分 | 授業の導入・目的説明 | 講義、質疑応答 |
| 30分 | 清拭・洗髪の手順と根拠説明 | 講義+デモンストレーション |
| 30分 | 学生による実技演習 | 実技指導、個別フィードバック |
| 20分 | 振り返り・質問タイム | グループディスカッション、質疑応答 |
各ステップで「学生が何をできるようになるか」を意識することで、授業の流れが明確になり、学生の理解度も把握しやすくなります。
教員1年目のリアルなつまずきと解決ヒント

完璧を目指さなくていい
教員1年目は、授業のたびに落ち込むことも珍しくありません。
でも、それは学生に真剣に向き合っている証拠です。授業は完璧である必要はなく、「伝えたい気持ち」が一番大切です。
AIも活用して授業準備をラクに
授業準備は大変ですが、AIを活用すれば効率化できます。
ただし、学生の反応や理解を引き出す工夫は、人間である教員にしかできません。AIはあくまでサポートツール。授業の核心部分は教員自身の役割です。
まとめ|授業は伝えたい気持ちが一番大事
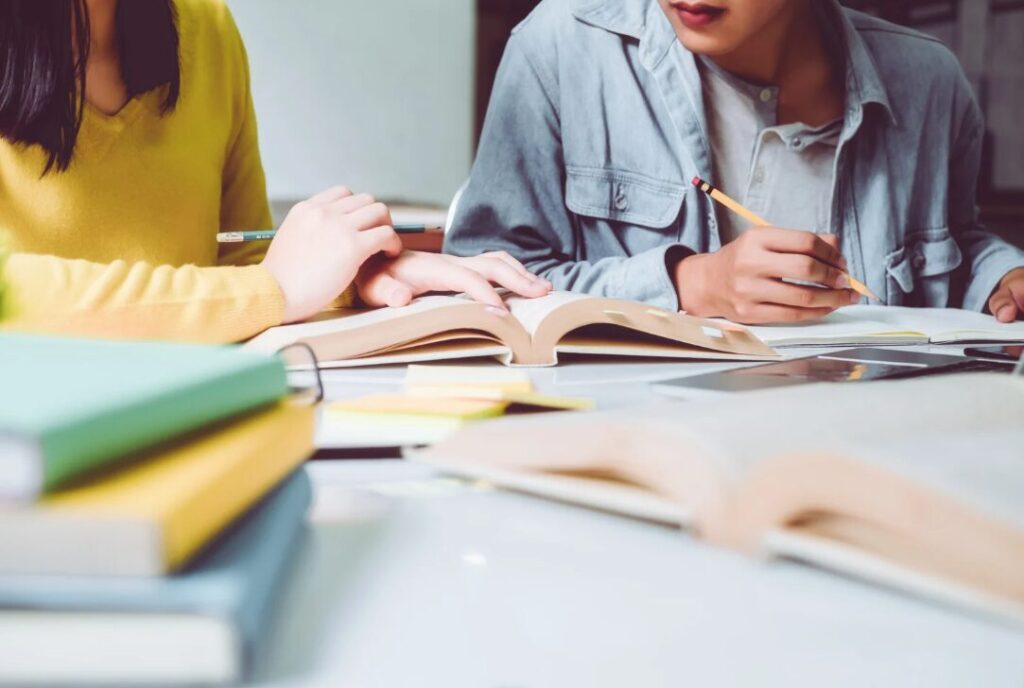
看護教員1年目の授業づくりは、戸惑いや不安が多いのは当然です。
- 「伝わっていない気がする…」
- 「もっと上手に教えたい…」
そんなときに大切なのは、完璧さではなく、学生に伝えたい気持ちを持つことです。授業は一度で完璧にできなくても大丈夫。少しずつ、学生が反応してくれる感覚や理解してくれる瞬間を積み重ねることが成長につながります。
私も伴走者として、あなたの授業づくりをサポートします。一緒に少しずつ、伝わる授業の感覚を育てていきましょう。