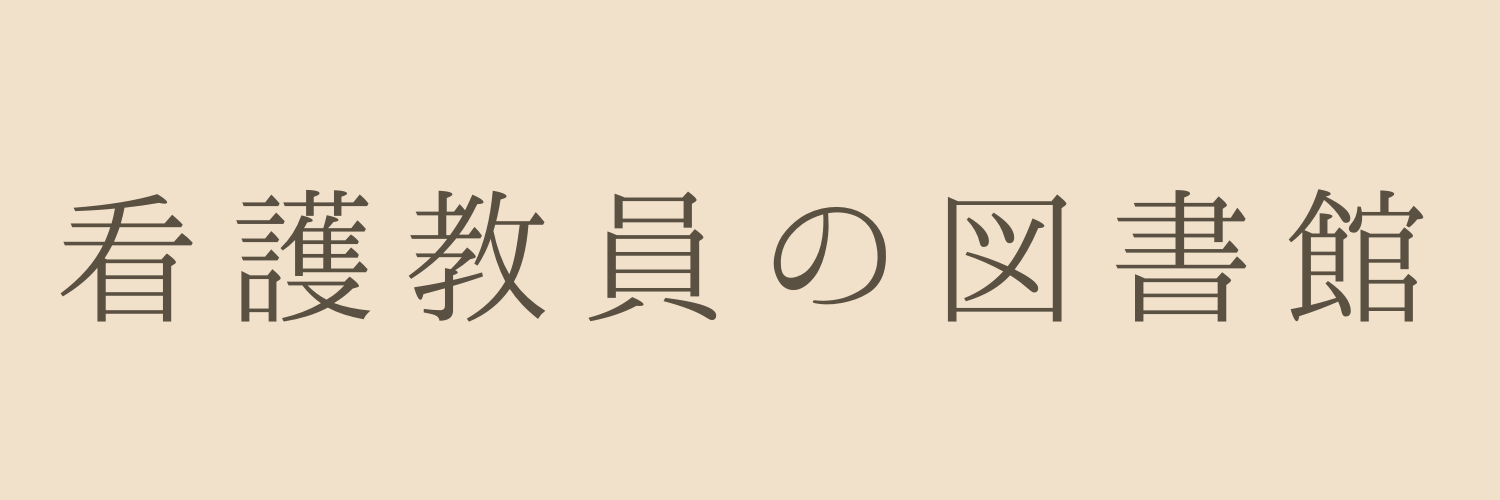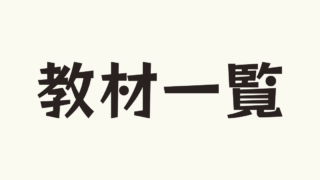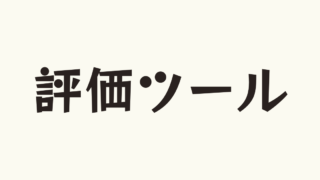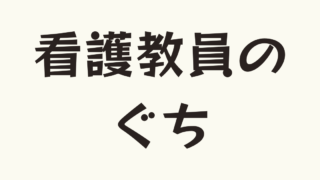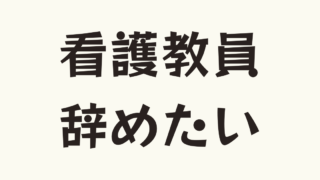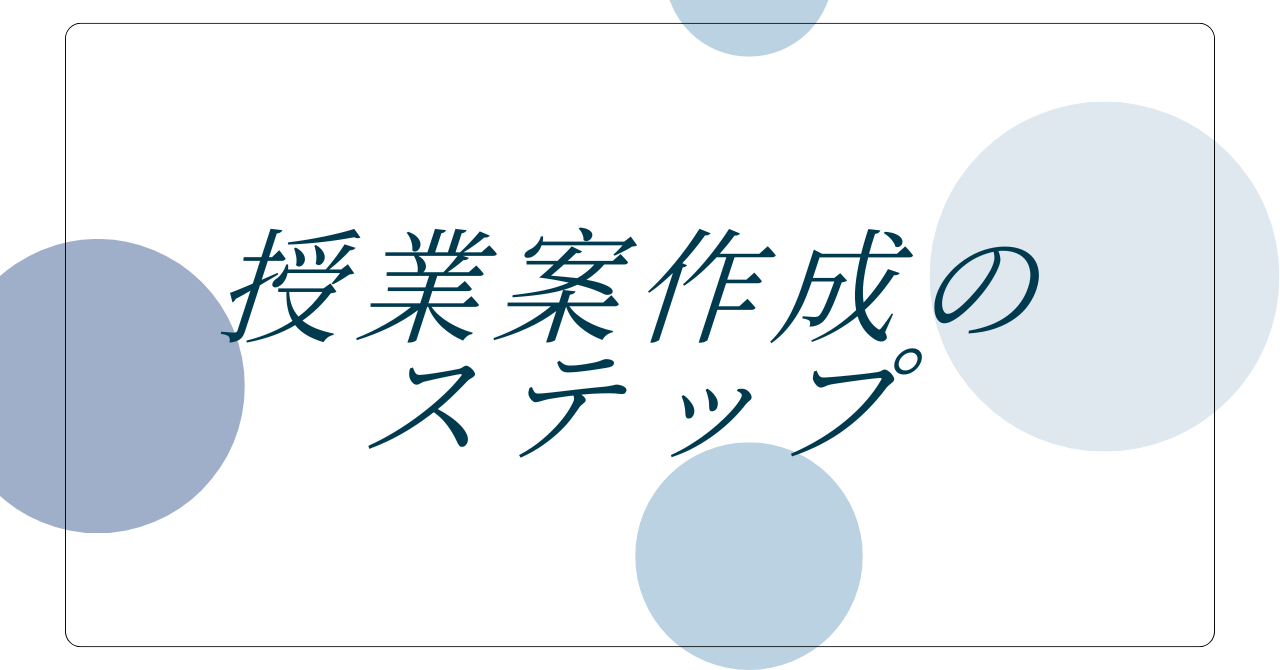授業案は、看護教育における授業の設計図であり、学生に効果的な学びを提供するために欠かせないものです。計画的に授業案を作成することで、教員自身の準備効率が向上し、授業の質も高めることができます。
本記事では、授業案を作成するためのテンプレートや授業を効果的に作るためのステップをご紹介します。これを参考にして、より良い授業作りに活かしていただければと思います。
また、本サイトでは看護教員向けの教材を科目ごとに整理しています。
ぜひ活用してくださいね。
クリック👉【看護教員向け】科目別授業案
授業構成テンプレート:Wordファイルダウンロード
人気記事👉【2026年】看護教員の転職ガイド
STEP1:授業テーマを決定する
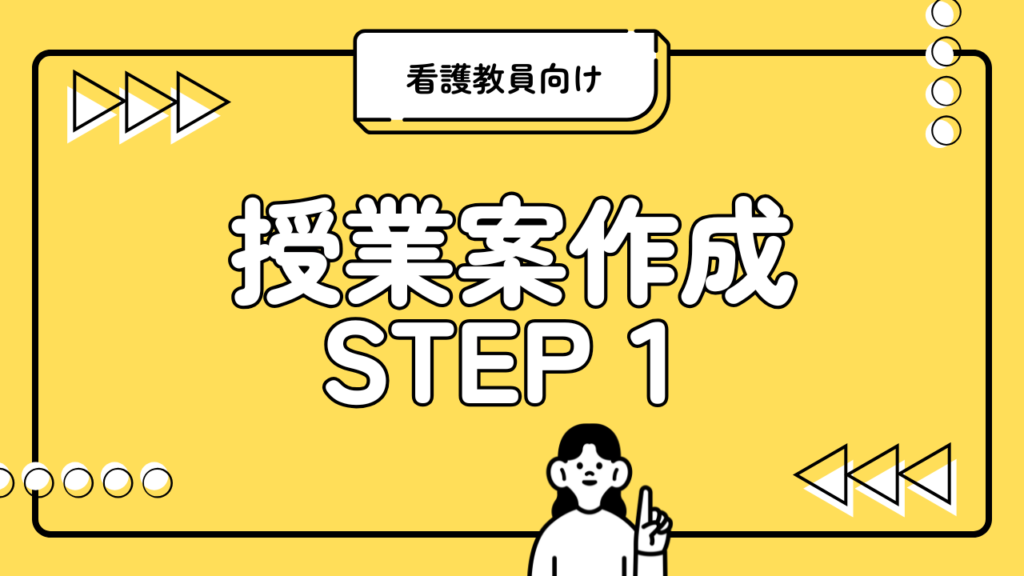
授業案作成の第一歩は、授業テーマを明確に決めることです。テーマを決める際は、カリキュラムとの整合性や学生の学年・習熟度を確認することが重要です。
具体例
- 看護過程のアセスメント技術
- 対象:3年生(基礎看護技術を習得済み)
- 内容:バイタルサインの観察・記録、症状の把握、必要な看護計画の立案
- BPSD(認知症の行動・心理症状)への対応
- 対象:4年生(老年看護学で認知症の基礎を学習済み)
- 内容:事例を基にしたケア計画の作成、グループでのディスカッション
💡 ポイント
授業テーマは「誰に・何を・どのレベルで教えるか」を明確にすることで、その後の目的設定や教材準備がスムーズになります。
STEP2:授業の目的を設定する

授業案作成では、学生に身につけてもらいたい知識・技術・態度 を明確に設定することが重要です。目的を具体化することで、授業内容や評価方法も組み立てやすくなります。
具体例
- 知識
- 疾患の病態と看護の関連性を理解する
- 例:COPD患者の呼吸管理で、症状や生活への影響を説明できる
- 技術
- 安全に看護技術を実施できる
- 例:吸引の手順を正しく実施し、感染予防策を遵守できる
- 態度
- 倫理的配慮の視点で患者に関われる
- 例:患者の生活背景や価値観を尊重してケア計画を立案できる
💡 ポイント
目的を具体化することで、授業内容、教材、アクティビティ、評価方法を一貫性のあるものにできます。
STEP3: 授業構成を検討する
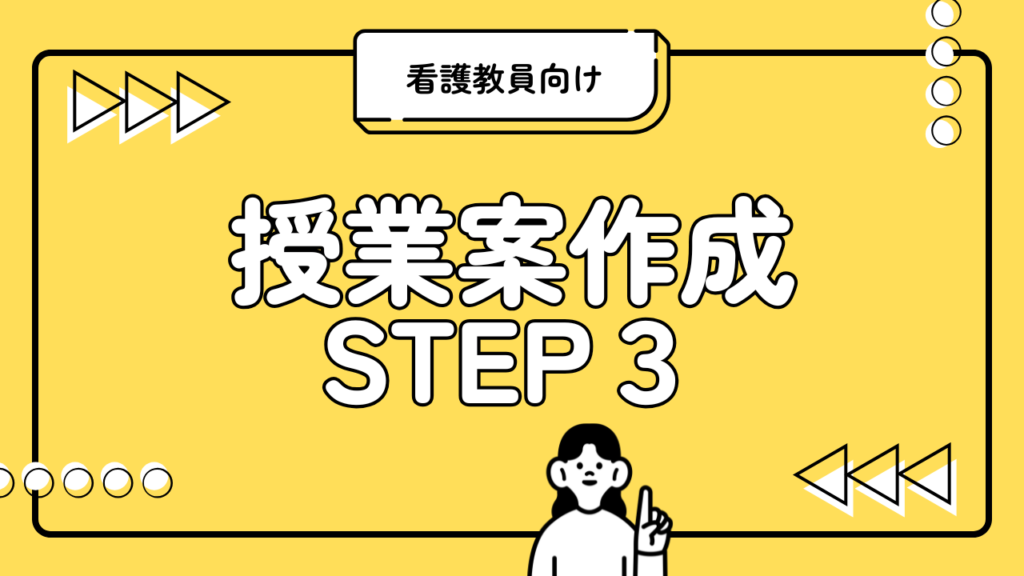
授業案作成では、授業を「導入・展開・まとめ」の3つのパートに分けて計画することが基本です。各パートで何を行うかを具体的に決めることで、授業の流れがスムーズになります。
(1)導入(約10分)
- 目的:学生の学習意欲を高め、授業への関心を引き出す
- 内容例:問いかけや事例提示
- 例:「COPD患者の呼吸管理で最も注意すべきことは何でしょうか?」
- ポイント:学生が主体的に考え始められる簡単な問いかけを設定する
(2)展開(約50分)
- 目的:知識を提示し、実践活動を通して理解を深める
- 内容例:スライドや板書での説明 → 演習やグループ活動
- 例:
- 吸引の手順を説明
- 模型を使った実技演習
- ペアで手順を確認し合う
- 例:
- ポイント:知識提示と演習を組み合わせることで理解度を高める
(3)まとめ(約30分)
- 目的:授業のポイントを振り返り、学びを定着させる
- 内容例:自己評価や次回授業への橋渡し
- 例:チェックリストを使って自己評価を行う
- 次回授業のテーマや課題を簡単に紹介する
- ポイント:振り返りを通して学生の理解度を確認し、次回の学習につなげる
💡 ポイント
- 導入・展開・まとめの時間配分を明確にすることで、授業中に迷わず進行できます。
- 各パートで「目的・内容・具体例・ポイント」を整理すると、授業案として完成度が高まります。
STEP4: 教材を準備する
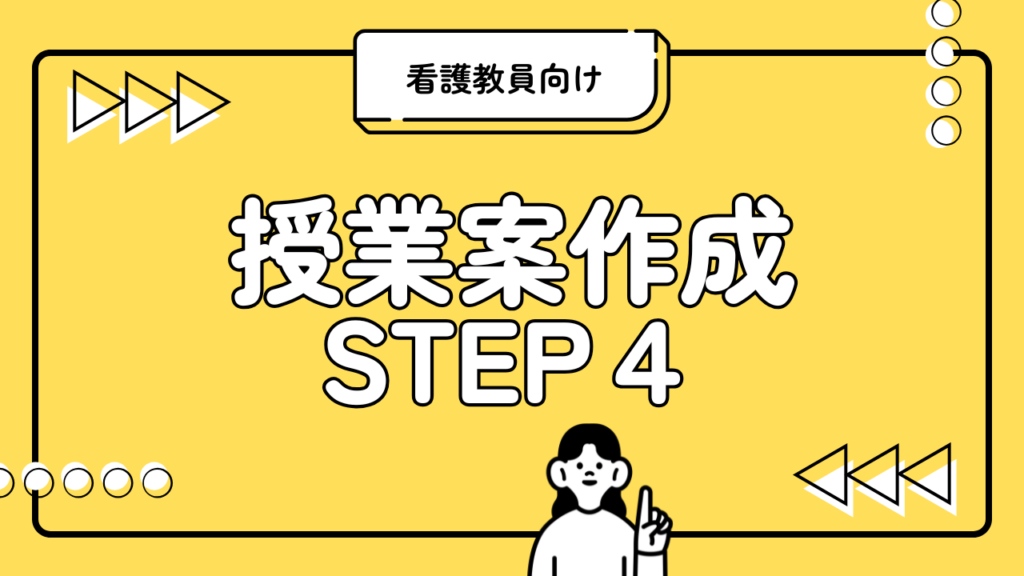
授業を効果的に進めるためには、必要な教材を事前に準備しておくことが重要です。教材の種類や活用方法をあらかじめ整理することで、授業中のスムーズな進行が可能になります。
(1)スライド
- 目的:視覚的に情報を整理し、理解を助ける
- 作成のポイント:
- 図表やイラストを多用してわかりやすくする
- キーワードを強調して学生の注意を引く
- 具体例:
- COPD患者の呼吸管理手順を図解で提示
- 吸引手順をステップごとにスライドにまとめる
(2)配布資料
- 目的:学生が授業内容を整理・復習できるようにする
- 準備方法:印刷配布、またはLMSにアップロード
- 具体例:
- 演習用ワークシート
- 振り返りシートやチェックリスト
- グループ討議用のケーススタディ資料
(3)映像・モデル
- 目的:実際の看護技術や患者の状況を視覚的に理解させる
- 活用例:
- 患者の介助シーンを動画で提示
- 吸引やポジショニングの実技モデルを使用
- 患者の声や症状の変化を記録した映像を紹介
💡 ポイント
スライド・配布資料・映像・モデルの3種類を組み合わせると、理解度が格段に向上します。
STEP5:アクティビティを計画する

授業では、学生が主体的に学べる演習や活動を組み込むことが重要です。アクティビティを通して、知識の理解を深め、技術や態度の習得を促します。
具体例
- BPSDの事例を用いたグループワーク
- 内容:認知症患者の行動・心理症状の事例を提示し、グループでケア計画を作成
- 目的:状況に応じたケア方法を考える力を養う
- 排泄援助のロールプレイ
- 内容:排泄援助の場面を学生同士で再現
- 目的:安全な手順や声かけの方法を体験的に学ぶ
- ポジショニングの実技指導とチェックリスト評価
- 内容:ポジショニングの手順を実践し、チェックリストで自己評価・相互評価
- 目的:正しい技術の習得と振り返りを行う
💡 ポイント
- アクティビティは「知識→技術→態度」の学びを体験的に結びつける場として活用する。
- 事前に目的や評価方法を設定しておくことで、授業の効果が高まります。
STEP6:評価方法を設定する
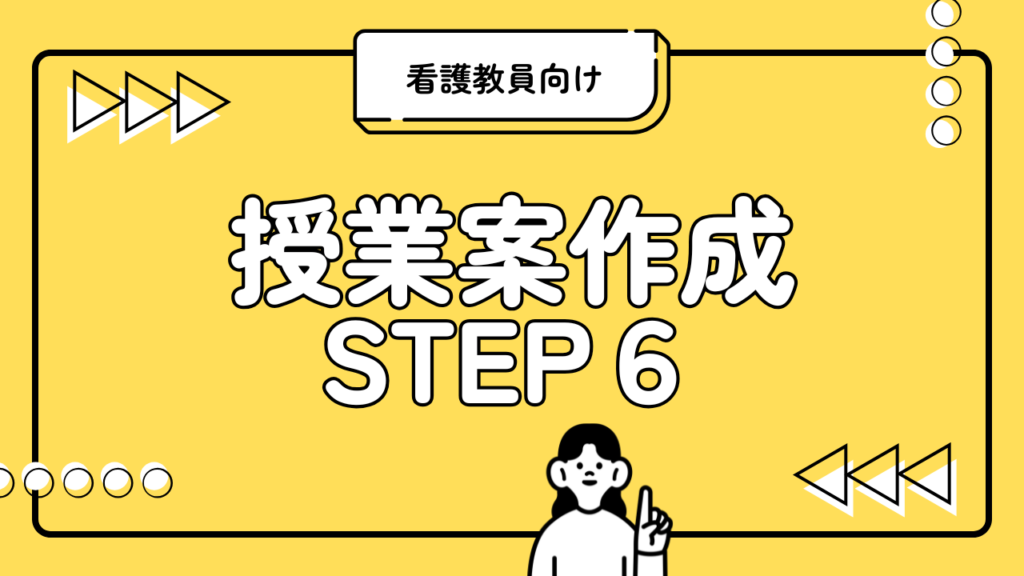
授業案では、授業中・授業後に学生の理解度や習得度を評価する方法を具体的に設定することが重要です。評価方法を事前に決めることで、学生へのフィードバックも的確に行えます。
(1)形成的評価(授業中)
- 目的:授業中の理解度や習熟度を把握し、指導に活かす
- 方法例:
- ワークやペアワークでの発言や行動の観察
- 演習中の手順の確認
- 学生への質問による理解度チェック
- ポイント:授業中に随時評価を行うことで、学生のつまずきを早期に修正できる
(2)総括的評価(授業後)
- 目的:学習全体の達成度を測定し、成績や次回の学習につなげる
- 方法例:
- レポート課題の提出・評価
- 演習記録やチェックリストによる技術の習熟度確認
- ケーススタディの提出内容の評価
(3)フィードバック
- 目的:学生の学習を振り返らせ、理解を深める
- 方法例:
- 振り返りシートへのコメント
- グループごとの口頭フィードバック
- 必要に応じて個別面談で指導
💡 ポイント
- 形成的評価と総括的評価を組み合わせることで、授業の理解度を多角的に確認できます。
- フィードバックは具体的・建設的に行い、次の学習へのモチベーションにつなげることが重要です。
まとめ
授業案は、授業の全体像を整理し、効率的に運営するための重要なツールです。計画的に作成することで、学生にとって意味のある学びを提供でき、教員自身の授業準備の負担も軽減されます。
また、授業案テンプレートを活用することで、授業の計画や教材の準備が効率化されます。さらに、学生のニーズや学習スタイルを反映させながら、授業後に振り返りと改善を繰り返すことで、より質の高い授業を目指すことができます。
本教材のご利用にあたって
1. 教材の目的と活用方法について
本教材は、授業設計の「骨格」としてご活用いただくことを目的に作成しております。各教育機関のカリキュラムや学生の学習レベルに応じて、柔軟に調整・アレンジしていただくことを推奨しております。スライドや板書の追加、発問の工夫など、先生方それぞれの教育スタイルに合わせてご利用ください。
2. AIツールを活用した資料作成について
本教材は、AIツールを活用して初稿を作成し、その後、看護教員としての専門的な視点を反映させながら、内容の精査と調整を行っております。効率と質の両立を意識し、現場で実際に使いやすい資料となるよう整えておりますが、ご使用にあたっては、必ずご自身で内容やエビデンスをご確認のうえ、授業内容に適した最終的な調整をお願いいたします。
3. 商用利用および転載・再配布の禁止について
本教材は、非営利の教育目的に限定して提供しております。営利目的での利用や、本教材の文章・構成・形式などを無断で転載・複製・再配布すること、あるいは改変しての販売・提供などは固くお断りいたします。教育目的以外でのご利用や二次利用をご希望の場合は、事前にご連絡いただき、書面での許諾を得ていただく必要があります。
免責事項
- 本教材は、最新の情報に基づいて十分配慮のうえ作成しておりますが、医療・看護分野の知見は日々変化しております。ご利用の際には、最新のガイドラインや教科書、信頼性のある文献をご参照いただき、必要に応じて内容の確認や修正をお願いいたします。
- 本教材の利用によって生じた結果や損害について、当ブログ管理者は一切の責任を負いかねます。必ず利用者ご自身の責任において、内容をご確認・ご判断のうえご使用ください。