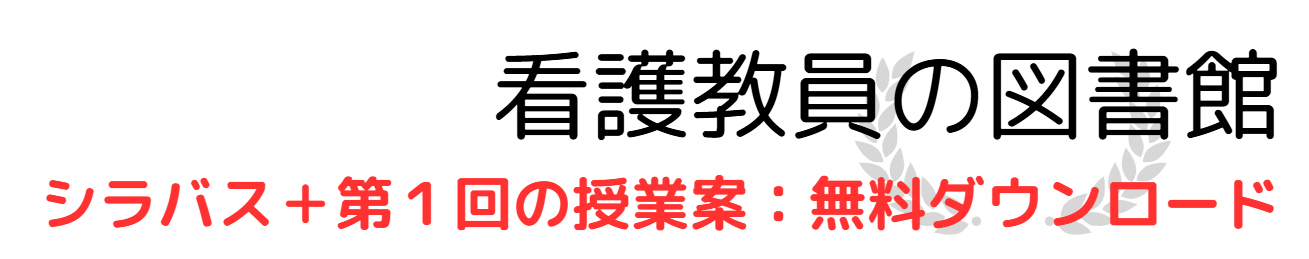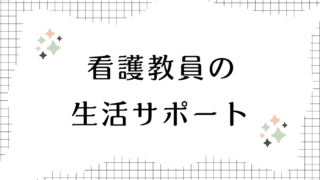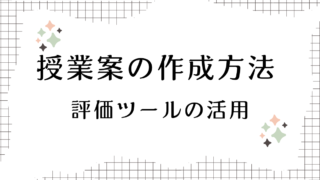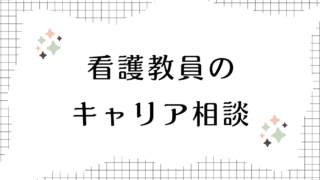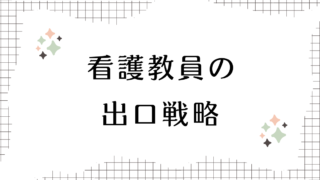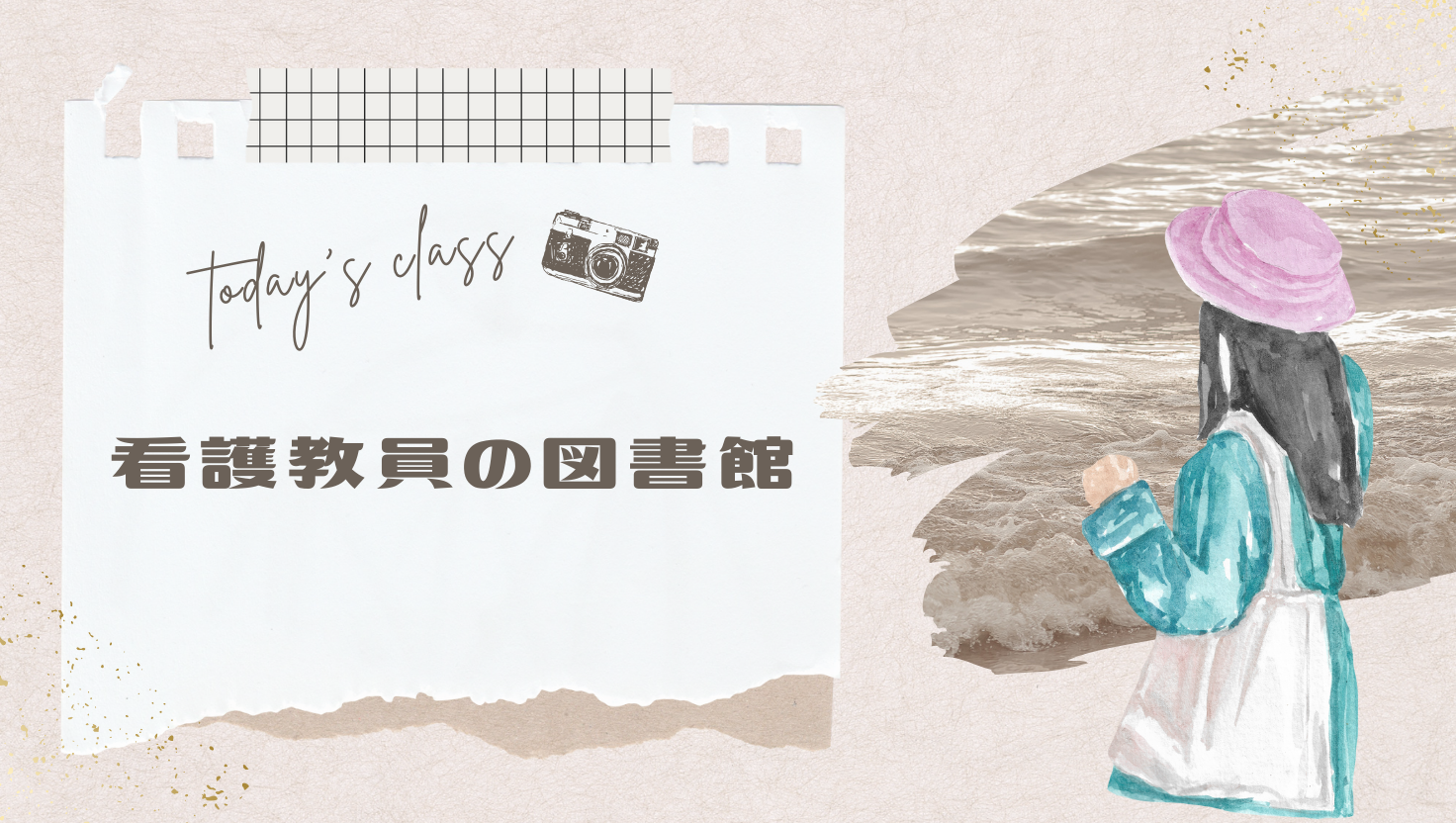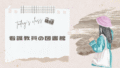看護教員として学生と関わっていると、「あれ、最近この子元気がないな」と感じる場面に出会うことがあります。
看護の学びはハードです。課題、実習、人間関係――心が疲れてしまう要因はたくさんあります。
本記事では、私自身の教員経験をふまえて、学生のメンタル不調に気づくサインや、教員としてできる関わり方についてご紹介します。
メンタル不調に気づくサイン
学生は必ずしも「つらい」とは言いません。以下のような変化に気づけたとき、それはサインかもしれません。
- 以前より表情が乏しくなった
- 遅刻や欠席が増えた
- 授業中の反応が極端に少ない
- 提出物の遅れや忘れが目立つ
- 周囲の学生から「最近あの子大丈夫ですか?」と声がかかる
小さな変化でも「何かあるかも」とアンテナを張っておくことが大切です。
教員としてできる“初期の関わり”
学生の不調に気づいたとき、いきなり深掘りしようとすると学生の警戒心を高めてしまうこともあります。まずは以下のような安心感のある関わりを心がけています。
- 声かけはさりげなく
「最近元気なかったけど、どうかした?」と、気軽に聞ける雰囲気づくりを意識します。 - プライベートを詮索しすぎない
相手が話してくれる範囲を尊重します。沈黙の時間も大切に。 - 共感と受容を優先する
「そんなことで落ち込まないで」ではなく、「つらかったね」「気づかなくてごめんね」と返すだけで救われる学生もいます。
必要に応じて専門職・他部署と連携する
学生の話を聴いている中で、「これは専門的な支援が必要かもしれない」と感じたら、一人で抱え込まず、学内の専門機関と連携します。
- 学生相談室(カウンセラー)への紹介
- 担任や学科主任との情報共有
- ケースによっては保健管理室、保護者との連携も視野に
私たち教員が“聞き役”として寄り添うことも大切ですが、支援の限界を知ることもまた、専門職としての責任です。
普段からの関係づくりが支援の土台に
学生が「この先生になら話せる」と感じてくれるかどうかは、日ごろの関わり方にかかっています。
- 小さな変化に気づいたら言葉をかける
- 雑談の中に安心感を生む
- 教員の価値観を押し付けない
- 「完璧じゃなくていいよ」と伝え続ける
日常的な安心感が、いざというときの支援につながるのだと思います。
まとめ
メンタル不調の学生と向き合うことは、正直、簡単なことではありません。
でも、私たち看護教員には「人を看る」視点があります。それを学生にも向けることで、教員としてできる支援はたくさんあるはずです。
「気づく」「寄り添う」「つなぐ」――この3つを意識しながら、無理のない範囲で支援を続けていきましょう。