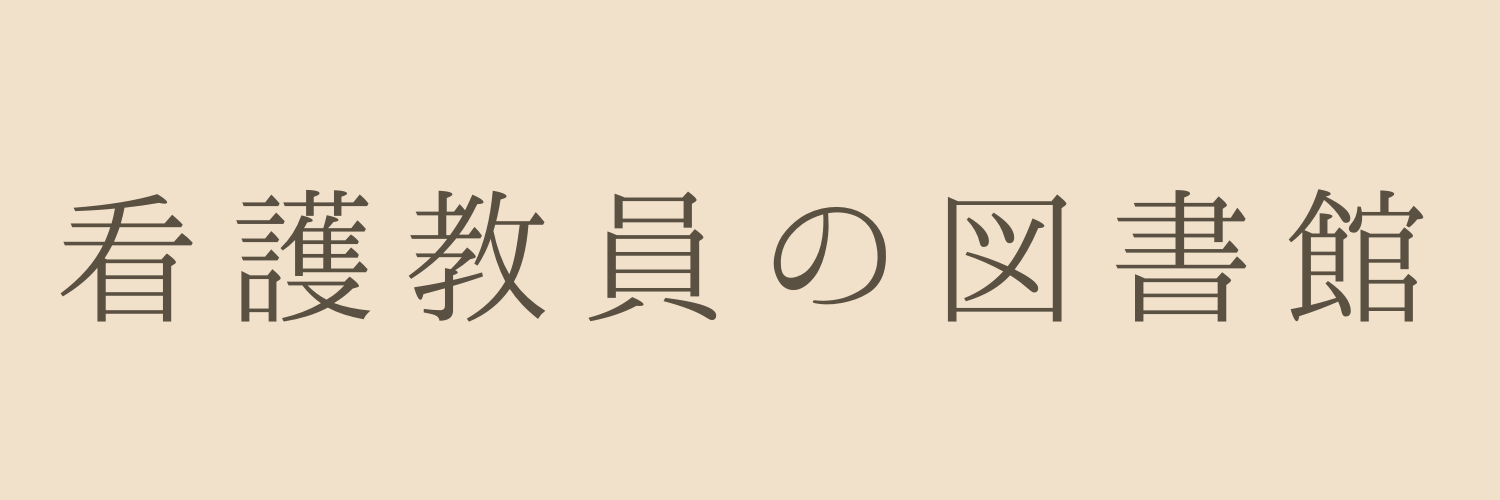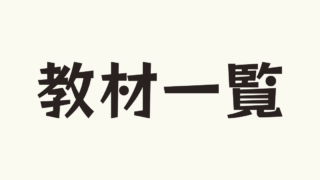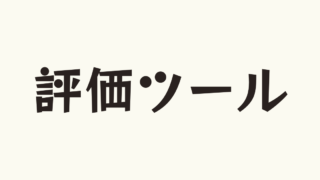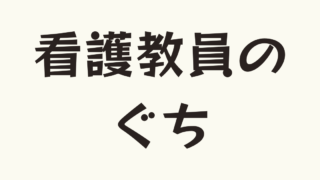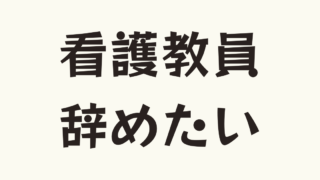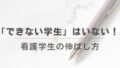看護教育も時代とともに変化していて、「ただ板書するだけ」「講義中心」では学生の学習効果が下がってしまいます。そこで、現代の学生に合った授業準備のポイントを紹介します。
このサイトでは看護教員向けの授業案がダウンロードできます。
クリック👉科目別:授業案まとめ
この記事の目次
1. 授業のゴールを明確にする

授業準備で最も重要なのは、「今日の授業を通して学生に何をできるようにするか」を明確にすることです。
具体例:授業ゴールの設定方法
例えば「看護過程」をテーマにした授業なら、次のようなゴールを設定できます。
実際の手順
- 授業開始前に「到達目標」を3つ程度、箇条書きにする
- 不要な情報はゴールと照らし合わせて削除
- 学生に授業冒頭でゴールを伝えることで、集中力が高まる
👉 ポイント:「とりあえずスライドを作る」のではなく、最初にゴールを決める。
90分間ずっと話すのではなく、15分話したら、5分考えさせるくらいのバランスが◎
2. 学生が主体的に学べるインタラクティブ要素を入れる
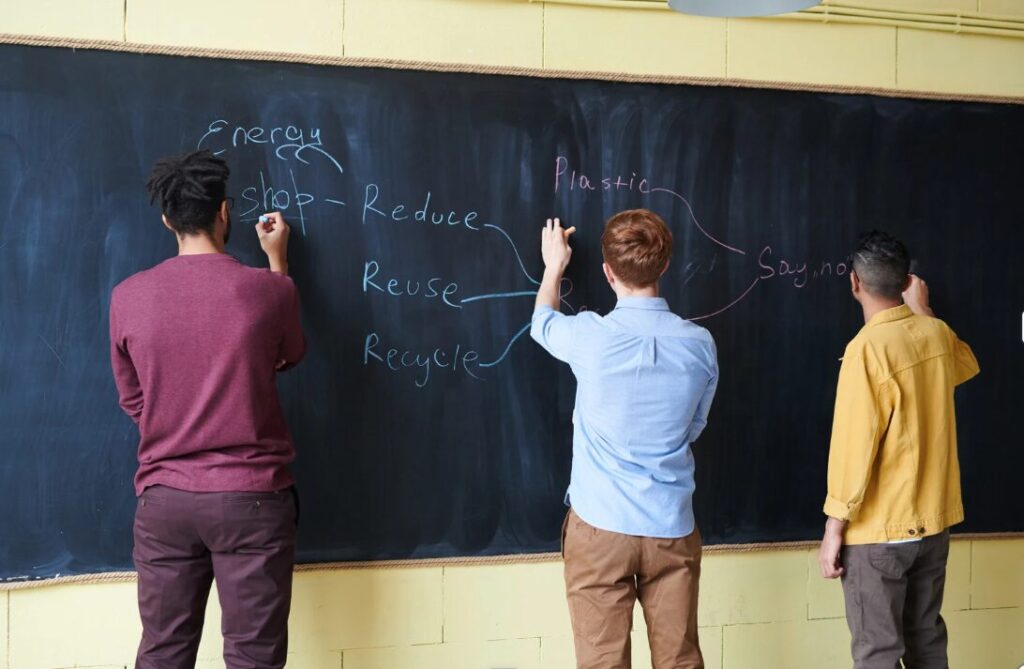
90分間ずっと講義すると、学生は集中力が途切れてしまいます。「聞くだけ」で終わらせず、考える・話す・動く要素を取り入れることが大切です。
授業に取り入れやすいインタラクティブ手法
時間配分の工夫
👉 ポイント:学生が「手を動かす時間」を必ず確保する。
3. スライドはシンプルに、画像・動画で理解を深める

授業準備で多くの教員が悩むのが「スライド作り」です。しかし、長文を詰め込むと学生は読むだけで終わり、学習効果は低下します。
悪い例
良い例
活用できるツール
👉 ポイント:スライドは「視覚で理解させるツール」として割り切る。
4. 学生のアウトプットを重視する

授業の目的は「先生が説明すること」ではなく、学生自身が説明できるようになることです。
具体的なアウトプット方法
👉 ポイント:学生が「受け身」から「主体的学習者」に変わる瞬間を作る。
5. 授業準備を効率化する時短テクニック

看護教員は授業だけでなく、実習指導や書類業務も多忙です。効率よく授業準備するためには「ゼロから作らない」ことが大切です。
時短の具体的な工夫
授業準備のルーチン例
- 1日目:授業ゴールを決める
- 2日目:スライドの骨組みを作る
- 3日目:クイズ・演習を準備
- 4日目:リハーサル・時間調整
👉 ポイント:準備の型を作れば、次回からは短時間で準備可能。
まとめ:現代風の授業準備は「学生主体」がカギ
これらを取り入れることで、学生の学習効果が上がり、授業準備の負担も軽減できます。