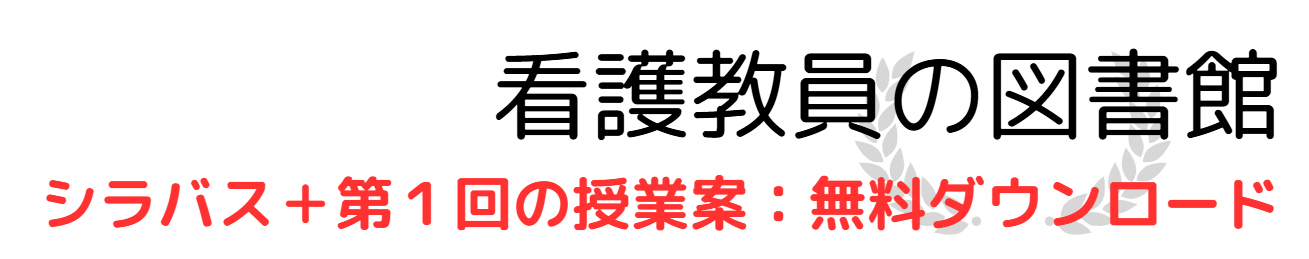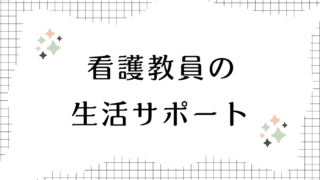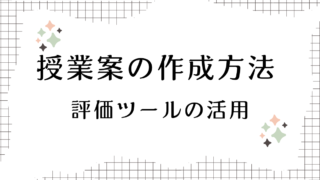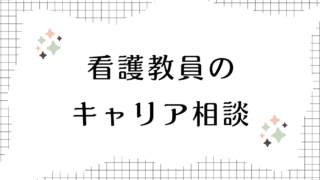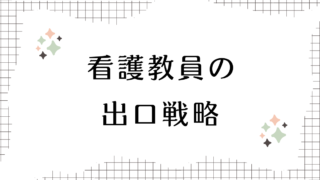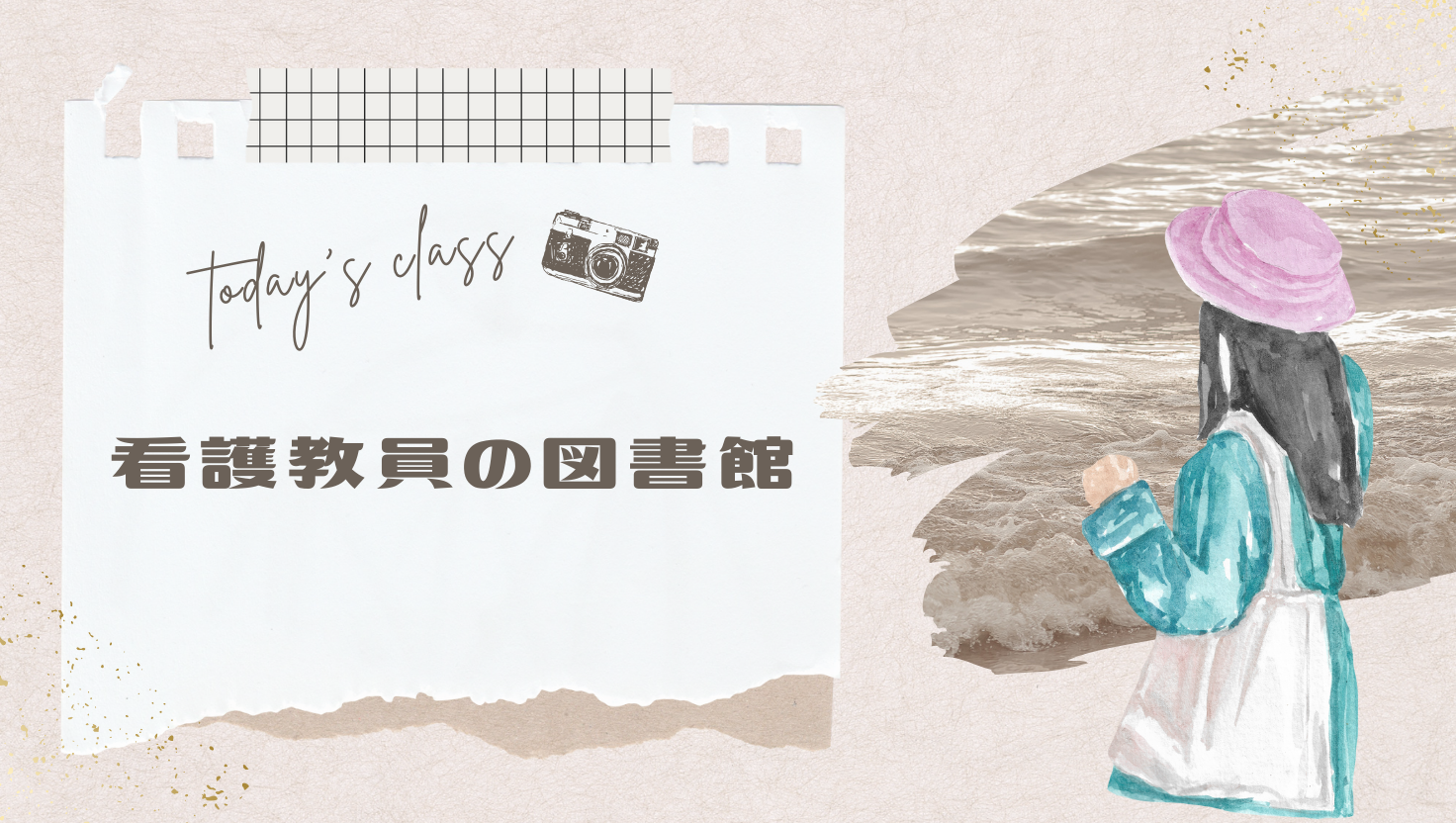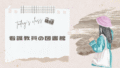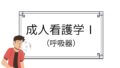看護教員って、本当にやりがいのある仕事ですよね。
学生の成長をそばで見守ることができて、自分の経験を次の世代に活かせる。でも、一方でふと立ち止まったとき、「なんで私、こんなに疲れてるんだろう…?」って感じることありませんか?
仕事に追われる日々の中で、自分の心と体のサインに気づきにくくなってしまうこともあります。今回は、看護教員のストレスの原因を振り返りながら、少しでも気持ちがラクになるヒントを一緒に考えてみたいと思います。
看護教員って、どんなことでストレスを感じてる?
臨床と教育のギャップに悩む
教科書に書いてあることと、実際の臨床って、やっぱり違うところがたくさんありますよね。
そのギャップを埋めながら教えるのって、けっこうエネルギーが要ります。しかも、カリキュラム変更やICT対応など、教員自身もアップデートし続けなきゃいけないプレッシャーがある。
「常に何かを学び続けなきゃいけない」「置いていかれたくない」そんな気持ちが、じわじわとストレスになっていきます。
とにかく業務が多すぎる
授業の準備に、レポートの添削、学生指導、実習の引率、委員会…。
もうスケジュール帳が真っ黒。気づけば休日もパソコンに向かってる…なんてことも珍しくありません。
「終わらない仕事」「減らないタスク」に、心も体もどんどん削られていく感じがしますよね。
学生対応の難しさ
最近の学生って、本当に多様です。
やる気がある子、どうしても集中できない子、体調が不安定な子…。一人ひとりと丁寧に関わりたいけど、正解がないからこそ悩んでしまう。
時には、保護者対応や管理職との間に挟まれることもあって、「自分のやり方、間違ってるのかな…?」と不安になることもあります。
教員同士の人間関係
教員同士でも、年齢や価値観が違うとすれ違いが起きやすいですよね。
教育方針や評価の考え方、学生への関わり方などでぶつかることも。
忙しい中でじっくり話す時間も取れず、モヤモヤを抱えたまま過ごしてしまう…。そんなことも、ストレスの原因のひとつになっていると思います。
評価のプレッシャー
特に実習評価って、ほんとに神経使います。
学生の未来に関わることだからこそ、責任重大。「この評価でよかったのかな」「この子、本当に卒業して大丈夫かな」って、悩んだ経験ありませんか?
寝る前にふと考えてしまって、眠れなくなる…そんな声もよく聞きます。
「私はこのままでいいのかな」という不安
臨床から離れて何年も経つと、「今の現場ってどんな風なんだろう?」「私の知識、古くなってない?」と不安になることがあります。
学生からの質問に答えられなかったとき、「あれ? 私、大丈夫かな…」って自信をなくしてしまうこともありますよね。
ストレスと上手に付き合うには
まずは「自分だけじゃない」と気づくこと
悩んでるのは、あなただけじゃありません。
私も、同僚も、みんな似たような思いを抱えています。だから、誰かにちょっと話すだけでも気持ちがラクになるんです。
職場の中で気軽に話せる人がいなければ、外部の勉強会やSNSコミュニティでつながりをつくってみるのもひとつの手です。
「完璧」を目指さなくても大丈夫
授業資料、もっと丁寧に作りたい。学生対応、もっとこうすればよかった…。そう思う気持ちは素晴らしいけれど、全部を完璧にやろうとしたら、体も心ももちません。「今日はここまででよし!」って、自分に合格点をあげる日があってもいいんです。
学生の“ちいさな成長”を見つけてみる
「先生、ありがとう」と言ってくれた。
昨日できなかったことが今日はできていた。そんな小さな変化や言葉って、あとからじわじわ効いてくるんですよね。
うまくいかなかったことばかりに目がいく日でも、ちょっとだけ目線を変えてみると、自分がやってきたことの意味が見えてきます。
自分のメンテナンス、後回しにしないで
教員って、誰かのために頑張るのが当たり前になっちゃってるけど、本当は自分のこともちゃんと大事にしてあげないといけないんです。
疲れたら休む。食べたいものを食べる。ちょっと贅沢なカフェでひとり時間を楽しむ。それだけでも、リセットできることってあります。
おわりに
看護教員って、本当に忙しいし、大変な仕事。
でも、学生の笑顔や成長を見られるっていう、かけがえのない魅力もありますよね。だからこそ、私たち自身が折れてしまわないように。
「頑張ってるよね、私」と、時には自分をぎゅっと抱きしめてあげてください。このブログが、あなたの心に少しでも寄り添えたなら嬉しいです。