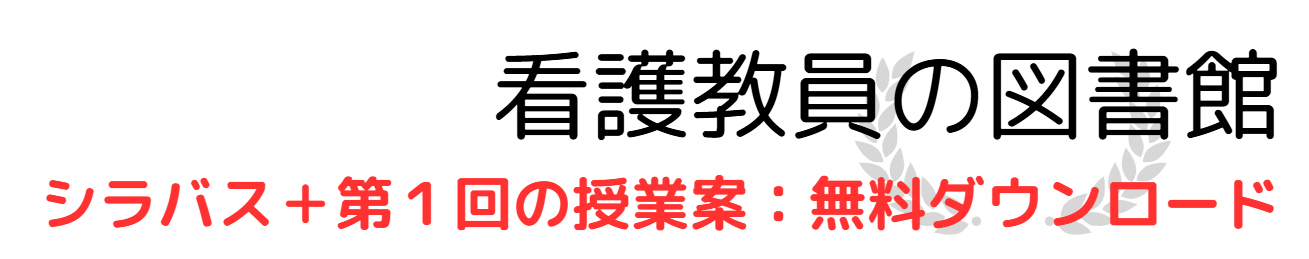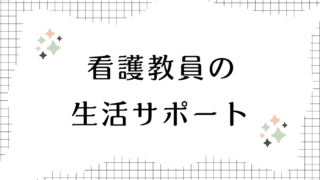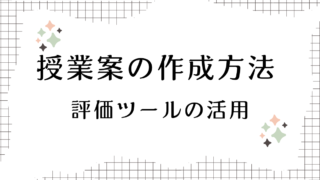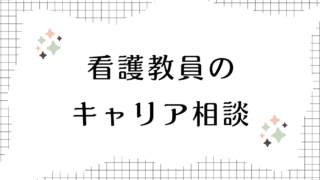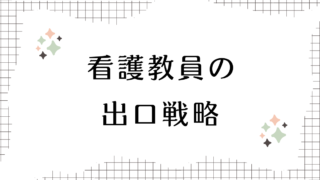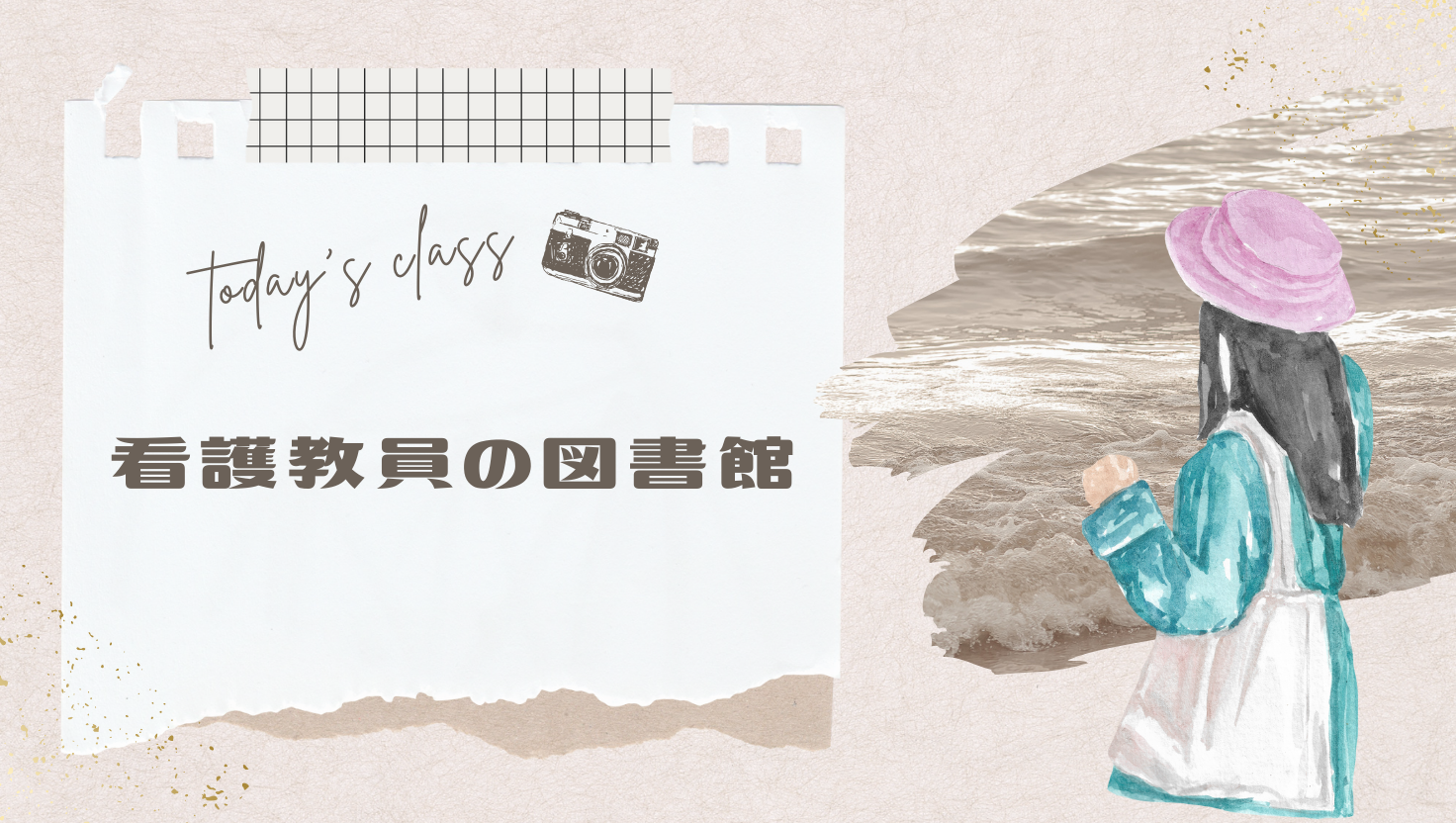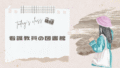「最近の学生、なんだか反応が薄いな…」
「もっと主体的に学んでほしいけど、どう関わればいいんだろう?」
いまの学生たちの多くは、いわゆるZ世代(1990年代後半~2010年頃生まれ)にあたります。
この世代は、デジタルネイティブとして育ち、SNSや動画など“速く・感覚的”な情報環境に慣れています。
看護教育の現場でも、彼らの学びのスタイルや価値観に合わせた支援が求められるようになってきました。
この記事では、Z世代の看護学生の特徴をふまえたうえで、教員としてどのように関わり、支援していけばよいかについて、いくつかの視点からヒントを紹介します。
Z世代の学生に見られる特徴
まずは、Z世代の学生によく見られる特徴を簡単に整理してみます。
- 情報の入手はスマホ中心:検索、動画視聴、SNSなどから効率よく収集
- 即時性を重視:結果や反応がすぐに返ってくることに慣れている
- 多様性に寛容:個人の価値観を尊重し、「こうあるべき」に疑問を持つ
- 視覚的・感覚的な理解に強い:文字よりも図や動画の方が頭に入りやすい
- 納得感が大切:「なぜ学ぶのか」が自分ごとにならないと動きにくい
これらの特徴を踏まえると、単に「教える」だけではなかなか伝わらない場面もあることが見えてきます。
学習支援のポイント
Z世代の看護学生に対する支援では、以下のような工夫が効果的だと考えられています。
「なぜ学ぶのか」を最初に伝える
単元の冒頭に、「この学びが将来どう活きるのか」「患者さんにどうつながるのか」といった目的や意義を明確に伝えることで、学生の関心が高まりやすくなります。
「この知識がどんな看護につながるのか?」という視点を持たせることが、モチベーションの土台になります。
一方通行の講義から対話的な場づくりへ
受け身で聞く時間が長くなると、集中力が続かない傾向があります。
短い問いかけやミニワークを取り入れたり、考える時間をあえて設けたりすることで、「考える→共有する→気づく」という流れをつくることができます。
正解を教えるよりも、「自分で答えを見つける」経験が、学びの定着につながります。
視覚的にわかりやすく
スライドやプリントに図やフローチャート、イラストを取り入れるだけでも、理解が深まることがあります。
また、スマホで見られる補助資料や解説動画を併用するのも、Z世代には相性の良い方法です。
情報を「見える化」することで、抽象的な概念も理解しやすくなります。
フィードバックは“具体的に・肯定的に”
Z世代は「どう評価されたか」よりも、「どう成長できたか」に価値を置く傾向があります。
「ここがよかった」「ここに気づいたのは大事」といった具体的で前向きなフィードバックは、次の行動につながる力になります。
努力や変化を言語化して伝えることで、自己効力感を高める支援が可能です。
最後に:関わり方を変えることは、支援の第一歩
Z世代だから特別というわけではありませんが、「伝わりにくい」と感じたとき、それは“学生側の問題”ではなく、“伝え方のアップデート”が必要なサインかもしれません。
学ぶ力を引き出すには、「教える」だけでなく「理解しようとする姿勢」も大切です。
Z世代の特徴をヒントに、より良い学習支援の形を一緒に考えていければと思います。
あとがき
看護教育の現場は、時代とともに変化しています。
Z世代の学生たちは、自分のスタイルで真剣に学ぼうとしている存在です。
その学びがより深く、豊かなものになるように、教員としてできることはたくさんあります。
小さな工夫の積み重ねが、彼らの未来につながっていく――
そう信じて、これからも教育の現場に向き合っていきたいですね。