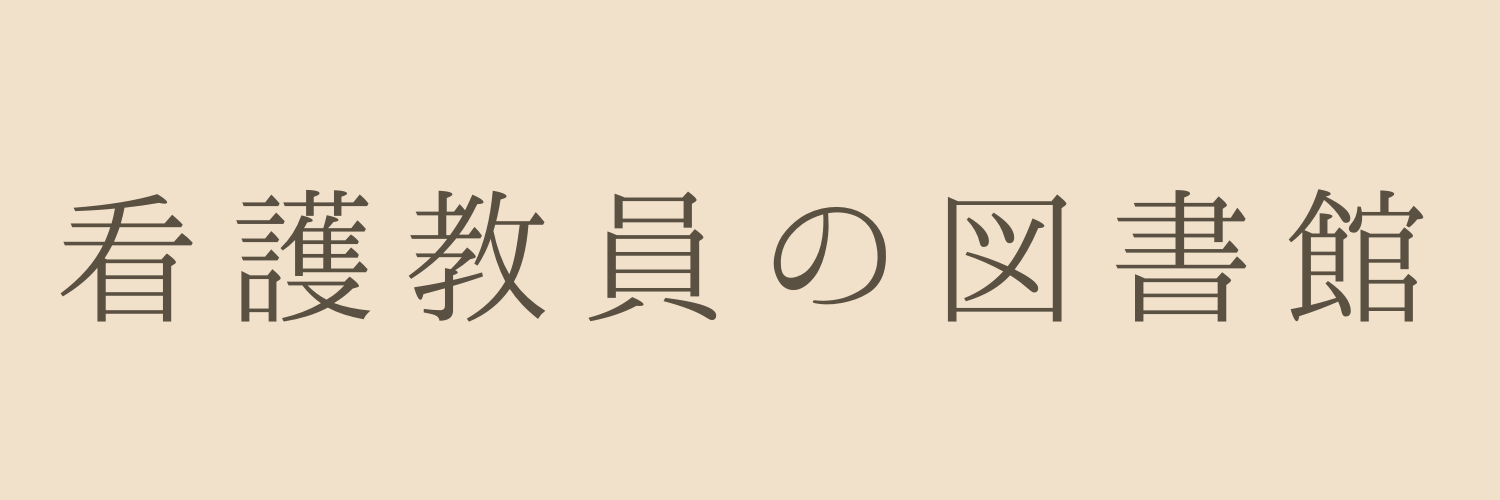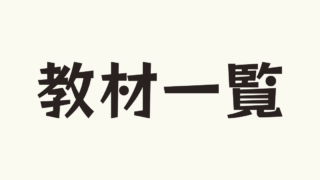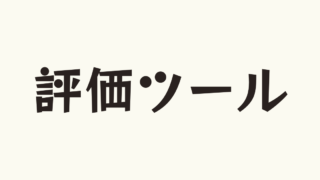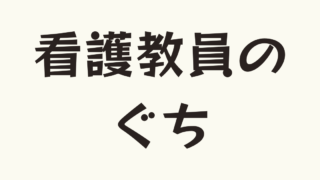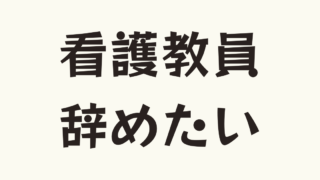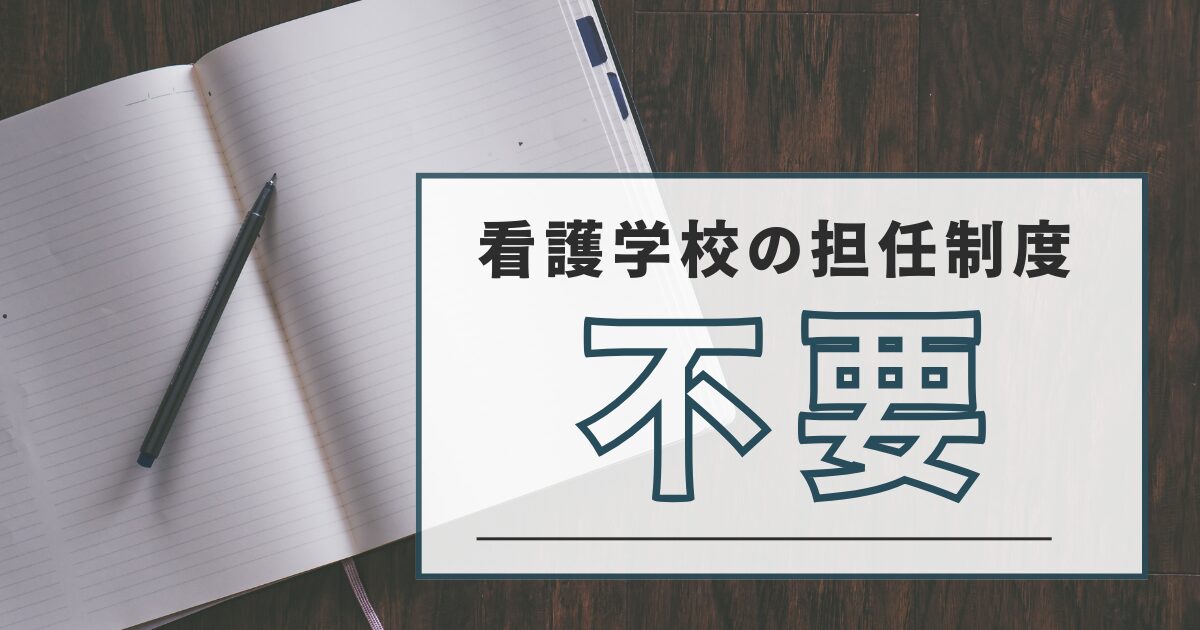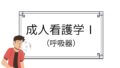看護専門学校では「担任教員(クラス担任)」を配置するのが当たり前のように行われてきました。学生指導や進路相談、生活支援など、多岐にわたる役割を担ってきた担任制度。 しかし、教員の働き方改革や教育の多様化が求められる今、あらためて「本当に担任は必要なのか?」を考える時期に来ています。
この記事では、看護教員としての現場経験をふまえ、担任制度は不要と考える理由を整理し、新しい支援体制のあり方を考えます。
このブログは看護教員向けの教材がDLできます💡
ぜひ授業でご活用下さい😊
クリック👉看護教員向け:科目別の授業案(ダウンロード教材)
担任制の本来の目的とは?

担任教員には、学生生活を幅広く支える役割が期待されてきました。主な内容は次の通りです。
- 学習・生活・進路の相談窓口
授業での学習方法や成績の悩み、アルバイトや人間関係、卒業後の進路相談まで幅広く対応する。 - 問題行動やメンタル不調の早期発見
遅刻・欠席の増加、態度の変化などから学生の異変をいち早く察知し、サポートにつなげる。 - 保護者・実習先との連携役
学生の状況を家庭や臨地実習先に伝え、橋渡し的な役割を果たす。 - 学生全体の統率・指導
クラス運営を円滑にし、行事や実習に向けたチームワークを高める。
このように担任は、いわば 学生の「何でも屋」 として寄り添う存在でした。
しかし近年は、こうした役割を 一人の教員に集中させること自体がリスク になりつつあります。教員の負担が過剰になり、学生支援が属人化することで、学校全体の支援体制が弱まる可能性があります。
看護教育において担任制が不要と考える3つの理由

1. 業務が属人化しすぎている
- 担任制では学生の情報(学習状況、生活面、メンタルの不調など)が一人の教員に集中しやすい。
- その結果、教員が異動・休職した際に、引き継ぎが難しくなり学生支援に大きな支障が出る。
- 情報共有が不十分だと、教員も学生も孤立し、サポート体制が崩れやすい。
👉 学生支援は「チームで共有」する仕組みが不可欠です。
2. 責任が重すぎるのに成果が曖昧
- 担任は「学生を卒業まで導く」ことを期待されるが、学習意欲や家庭環境、個人の性格など、担任の努力だけでは解決できない要素が多い。
- にもかかわらず、退学や問題行動が起きた際に「担任の責任」とされるケースが少なくない。
- そのため、担任は精神的にも時間的にも過剰な負担を抱えやすい。
👉 達成度が測りにくい責任を一人に押し付けるのは不合理です。
3. 学生は「担任」より「複数の教員」を求めている
- 学生の声としてよくあるのは「担任の先生には言えないけど、別の先生には相談できた」というケース。
- 学生の多様化に伴い、一人の担任にすべてを委ねるのはむしろ負担やプレッシャーになる。
- 複数の教員が支援する「チーム体制」の方が、学生にとって安心できる相談先となる。
👉 学生は「一人の担任」ではなく「複数の支援者」を必要です。
新しい学生支援体制:チームアプローチのすすめ

担任制を廃止しても、学生支援がなくなるわけではありません。むしろ、教員チームで分担することで、安定した支援と負担の軽減が可能になります。
チーム支援の具体的な方法
- 学年ごとに「担当教員チーム」を編成する
学年単位で複数教員が関わることで、情報や責任を分散できる。 - 進路・メンタル・学習支援を分担する
それぞれの専門性を生かし、教員が得意分野で学生をサポートできる。 - 学生情報を電子記録で共有する
誰でも対応できる体制を作り、教員の休職や異動があっても学生支援が途切れない。
👉 こうした仕組みを導入すれば、教員の負担を軽減しながら、学生にとって安心できる支援体制を実現できます。
まとめ|看護教育に担任制度は本当に必要か?
かつては担任制が最適だったかもしれません。しかし、看護教育の現場は変化しています。
これらを考えると、担任制は「不要」になりつつあるといえるでしょう。
重要なのは「今までそうだったから続ける」ではなく、「これからどうあるべきか」を基準に制度を見直すことです。
👉 あなたの学校では、担任制度についてどんな議論がありますか?現場の声を大切に、これからの看護教育のあり方を一緒に考えていきましょう。