この記事の目次
科目
日常生活援助技術Ⅱ(食事、排泄)
科目の目的
日常生活の基本的援助技術のうち、食事および排泄に関する援助について、対象の状態を適切にアセスメントし、安全で尊厳を守る実践的な援助が行える基礎的能力を養う。
到達目標
- 食事および排泄に関する援助技術の基本的知識を理解する。
- 対象の状態に応じた食事・排泄援助の選択と実践ができる。
- 援助の際の安全管理、プライバシー保護、感染予防に配慮した行動がとれる。
- 摂食嚥下障害や排泄障害を有する対象に対し、根拠に基づいた援助を説明できる。
- 食事・排泄援助に関する記録・報告・連携が適切に行える。
授業構成(全10回)
第1回:食事援助の基本
- 食事援助の目的と看護における意義
- 食事援助に必要な基本的知識(栄養、食事の形態、文化的背景)
- 援助時の観察ポイント(食欲、摂取量、体位、表情など)
- 安全な食事援助に必要な姿勢・環境整備
第2回:食事摂取の援助
- 食事環境の整え方とその意義(安心・自立の促進)
- 自力摂取困難な対象への介助方法(スプーンの使い方、声かけ)
- 安楽なポジショニングと体位保持の実際
- 介助中の観察項目とフィードバックの仕方
第3回:摂食・嚥下の仕組みと障害
- 摂食嚥下の5期(先行期~食道期)の生理学的理解
- 嚥下障害のサイン(むせ、咳、湿性嗄声など)
- 疾患や障害による嚥下機能の変化
- 嚥下評価の基本的観察とアセスメント視点
第4回:摂食嚥下障害への援助技術
- 嚥下障害への間接訓練・直接訓練の種類と目的
- 食形態の工夫(ミキサー食、ソフト食など)
- とろみ剤の種類と調整の仕方
- 誤嚥防止のための食事介助技術と口腔ケアの関連性
第5回:経口以外の栄養摂取の援助
- 経管栄養(経鼻胃管・胃瘻)の適応と概要
- 栄養注入時の体位管理と観察ポイント(誤嚥、腹部膨満など)
- チューブ挿入部位のケアと感染予防
- 栄養剤の管理と注入速度への配慮
第6回:排泄援助の基本
- 排泄の生理(排尿・排便のメカニズム)
- 排泄援助の基本的考え方(自立支援・尊厳保持)
- 排泄パターンの観察とアセスメント
- 排泄環境(トイレ、ポータブルトイレ、オムツなど)の整備
第7回:自然排尿・排便の援助
- トイレ誘導のタイミングと方法
- 排泄のタイミング把握の重要性(生活リズムの理解)
- オムツ交換の手順と皮膚トラブル予防
- 寝たきり対象への排泄援助の工夫
第8回:導尿技術の基礎
- 導尿の目的と適応・禁忌
- 無菌操作の基本と導尿実施の手順
- カテーテルの種類と選択基準
- 合併症予防(感染、損傷など)と観察項目
第9回:排便を促す援助技術
- 排便パターンのアセスメント方法(便秘、下痢、失禁など)
- 下剤の種類と特徴(刺激性、浸透圧性など)
- 浣腸・摘便の実施手順と留意点
- 排便時の羞恥心軽減への配慮、説明の工夫
第10回:排泄に関する複雑な援助とその対応
- 疾患や手術による一時的・慢性的排泄障害への援助
- 排尿日誌や排泄記録を活用したケアの立案
- 看護師としての判断が求められる援助(導尿の継続・中止など)
- 失禁用具・排泄補助具の種類と使い方(尿器、差し込み便器など)
本教材のご利用にあたって
1. 教材の目的と活用方法について
本教材は、授業設計の「骨格」としてご活用いただくことを目的に作成しております。各教育機関のカリキュラムや学生の学習レベルに応じて、柔軟に調整・アレンジしていただくことを推奨しております。スライドや板書の追加、発問の工夫など、先生方それぞれの教育スタイルに合わせてご利用ください。
2. AIツールを活用した資料作成について
本教材は、AIツールを活用して初稿を作成し、その後、看護教員としての専門的な視点を反映させながら、内容の精査と調整を行っております。効率と質の両立を意識し、現場で実際に使いやすい資料となるよう整えておりますが、ご使用にあたっては、必ずご自身で内容やエビデンスをご確認のうえ、授業内容に適した最終的な調整をお願いいたします。
3. 商用利用および転載・再配布の禁止について
本教材は、非営利の教育目的に限定して提供しております。営利目的での利用や、本教材の文章・構成・形式などを無断で転載・複製・再配布すること、あるいは改変しての販売・提供などは固くお断りいたします。教育目的以外でのご利用や二次利用をご希望の場合は、事前にご連絡いただき、書面での許諾を得ていただく必要があります。
免責事項
- 本教材は、最新の情報に基づいて十分配慮のうえ作成しておりますが、医療・看護分野の知見は日々変化しております。ご利用の際には、最新のガイドラインや教科書、信頼性のある文献をご参照いただき、必要に応じて内容の確認や修正をお願いいたします。
- 本教材の利用によって生じた結果や損害について、当ブログ管理者は一切の責任を負いかねます。必ず利用者ご自身の責任において、内容をご確認・ご判断のうえご使用ください。
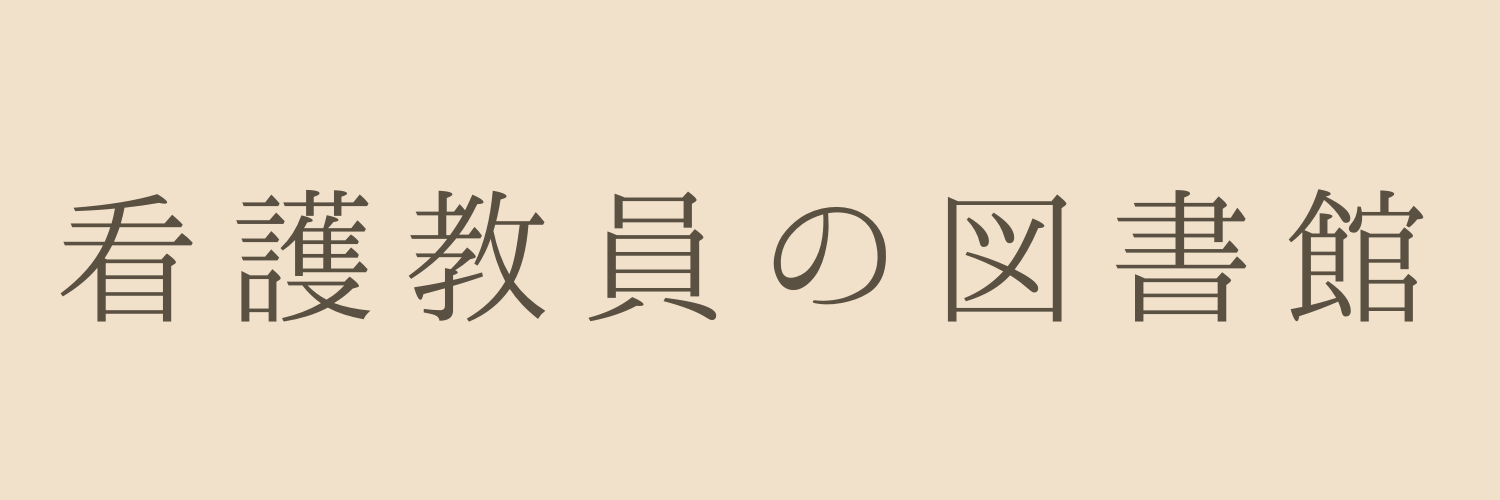
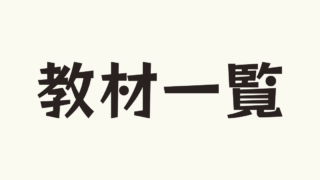
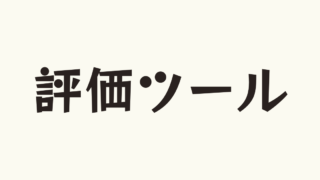
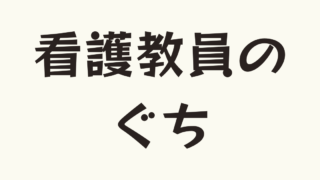
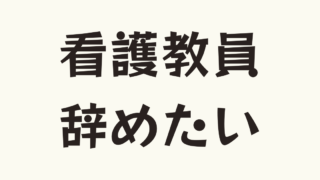
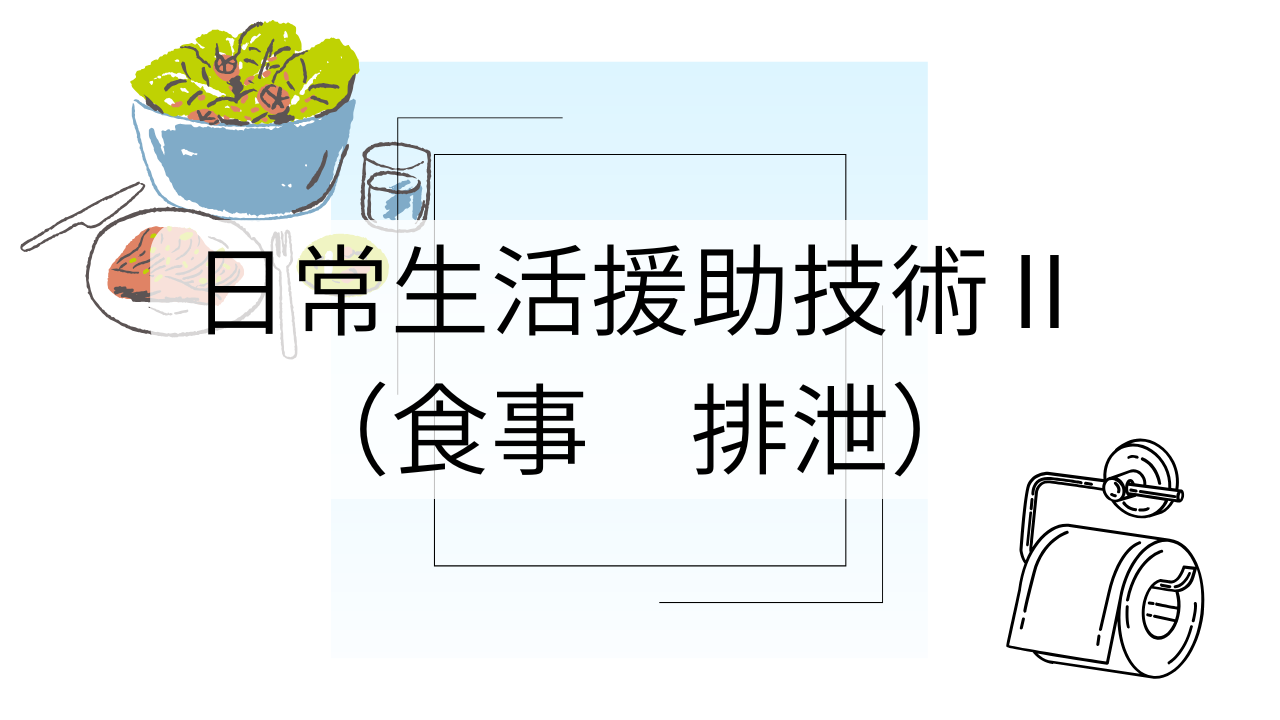

サムネ-1-120x68.png)