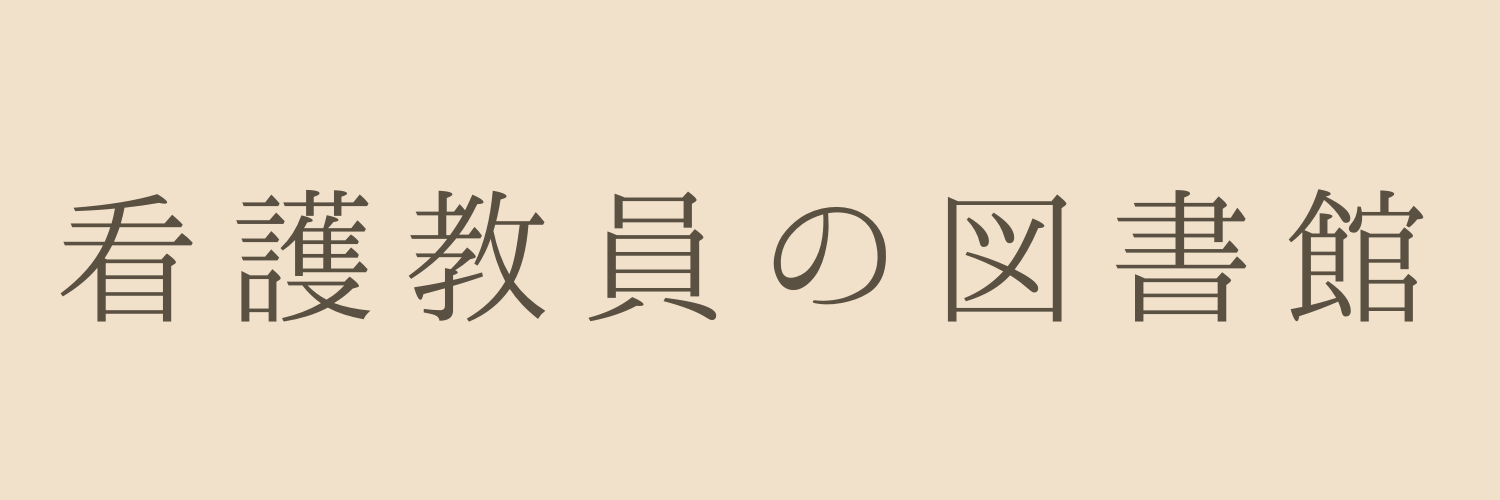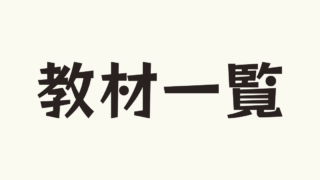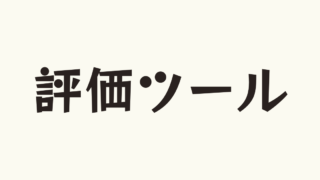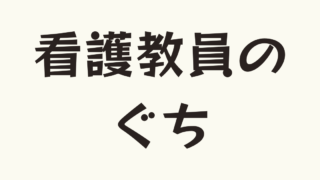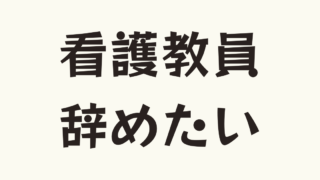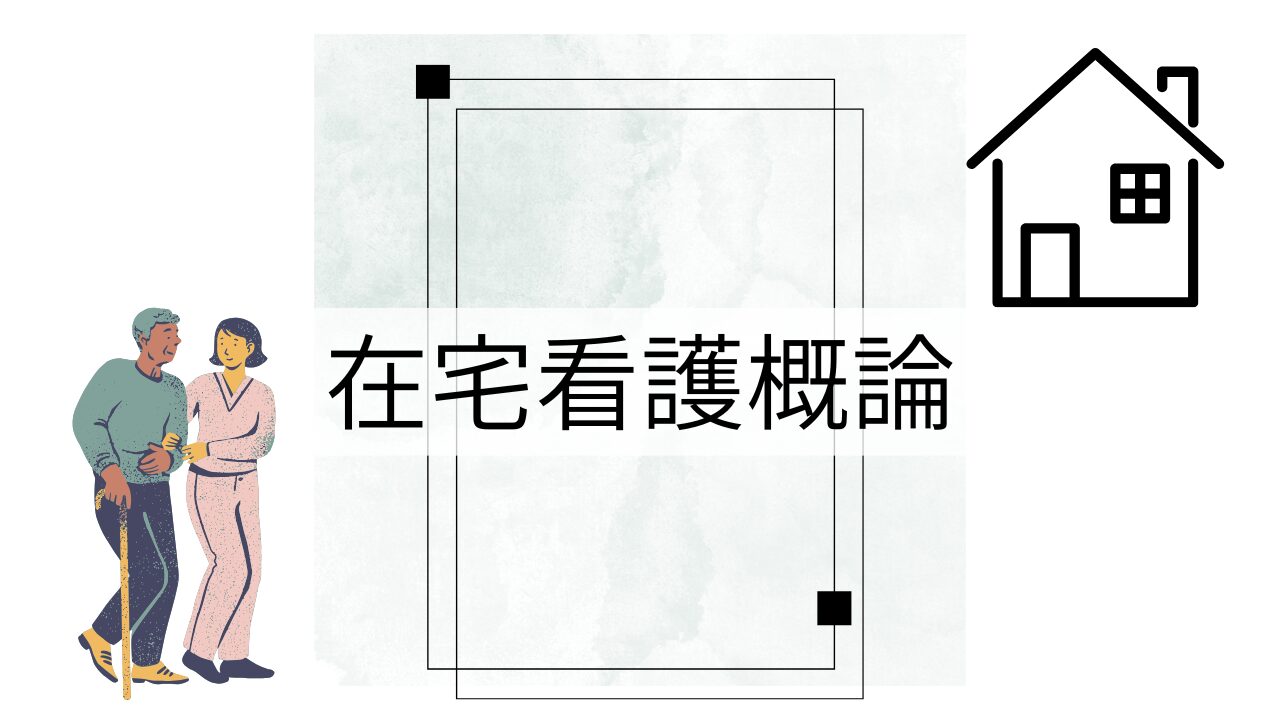この記事の目次
科目名
在宅看護概論
目的
在宅療養を支える看護の基盤的理解を深め、地域で生活する療養者とその家族に対する看護の視点と役割を理解する。社会的背景や制度、在宅における特有の課題についても学び、今後の在宅看護実践に必要な基礎的知識を修得する。
目標
- 在宅看護の基本的な概念と看護師の役割を説明できる
- 社会構造や制度、在宅看護に影響する背景を説明できる
- 在宅看護における看護倫理や権利擁護の考え方を理解できる
- 在宅療養におけるリスクや安全管理の重要性を説明できる
- 在宅看護に関わる制度や社会資源を活用した支援について説明できる
授業構成(全8回・各回90分)
第1回:在宅看護の基本と看護師の役割
- 在宅看護の定義と目的
- 在宅療養を支える看護の意義と必要性
- 在宅看護における看護師の役割と実践領域
- 在宅療養者・家族のニーズと在宅看護の対応
- 病院看護との違い、生活支援の視点
第2回:看護の変遷と社会・家族構成の変化
- 看護の歴史と医療の場の変遷(施設から在宅へ)
- 少子高齢化、核家族化など社会的背景の変化
- 家族形態の多様化とケア提供の実際
- 地域包括ケアシステムの概要と在宅看護との関連
- 在宅療養を支える社会的仕組みと課題
第3回:在宅看護における看護倫理と権利擁護
- 在宅看護における倫理的配慮(プライバシー、尊厳など)
- 患者の意思決定支援とインフォームド・コンセント
- 認知症や意思表出困難な対象への対応
- 看取りのケアと意思の尊重
- 権利擁護の必要性と虐待の防止
第4回:在宅看護の対象と生活支援
- 在宅看護の対象となる人々(慢性疾患、難病、障害児・者、ターミナルなど)
- 各対象に応じた看護の視点
- 自立支援とQOLの向上を目的とした看護
- 家庭内の生活環境とケアの調整
- 対象に応じた在宅ケアの課題と工夫
第5回:在宅看護の提供方法と訪問看護制度
- 訪問看護の仕組みとサービス内容
- 通所・短期入所・訪問診療との連携
- 訪問看護ステーションの役割と機能
- 利用者とサービス提供者の関係構築
- 訪問看護の実際の流れ(アセスメント、計画、実施、評価)
第6回:入退院支援と医療・施設間の連携
- 入退院支援における看護師の役割
- 医療機関と在宅間の情報連携の重要性
- 多職種連携の具体例(病院、訪問看護、ケアマネ、薬剤師など)
- 地域包括ケア会議・退院前カンファレンスの活用
- 継続看護を実現するためのポイント
第7回:在宅看護におけるリスクマネジメント
- 在宅で起こりやすい事故とその要因(転倒、誤薬、窒息、火傷など)
- 医療機器の使用に伴うリスク(在宅酸素、カテーテル類など)
- 感染予防対策と清潔ケアの実際
- 高齢者や障害者への虐待リスクと防止
- 家族や介護者の負担とバーンアウトの予防
第8回:法令・制度・社会資源の理解と活用
- 在宅看護に関する主要な法制度(医療法、介護保険法、障害者総合支援法など)
- 訪問看護における制度的枠組みと報酬体系
- 社会資源(地域包括支援センター、福祉用具、民間支援など)の種類と使い方
- ケアマネジメントの視点と連携の在り方
- 制度を活かした継続支援と地域とのつながり
本教材のご利用にあたって
1. 教材の目的と活用方法について
本教材は、授業設計の「骨格」としてご活用いただくことを目的に作成しております。各教育機関のカリキュラムや学生の学習レベルに応じて、柔軟に調整・アレンジしていただくことを推奨しております。スライドや板書の追加、発問の工夫など、先生方それぞれの教育スタイルに合わせてご利用ください。
2. AIツールを活用した資料作成について
本教材は、AIツールを活用して初稿を作成し、その後、看護教員としての専門的な視点を反映させながら、内容の精査と調整を行っております。効率と質の両立を意識し、現場で実際に使いやすい資料となるよう整えておりますが、ご使用にあたっては、必ずご自身で内容やエビデンスをご確認のうえ、授業内容に適した最終的な調整をお願いいたします。
3. 商用利用および転載・再配布の禁止について
本教材は、非営利の教育目的に限定して提供しております。営利目的での利用や、本教材の文章・構成・形式などを無断で転載・複製・再配布すること、あるいは改変しての販売・提供などは固くお断りいたします。教育目的以外でのご利用や二次利用をご希望の場合は、事前にご連絡いただき、書面での許諾を得ていただく必要があります。
免責事項
- 本教材は、最新の情報に基づいて十分配慮のうえ作成しておりますが、医療・看護分野の知見は日々変化しております。ご利用の際には、最新のガイドラインや教科書、信頼性のある文献をご参照いただき、必要に応じて内容の確認や修正をお願いいたします。
- 本教材の利用によって生じた結果や損害について、当ブログ管理者は一切の責任を負いかねます。必ず利用者ご自身の責任において、内容をご確認・ご判断のうえご使用ください。